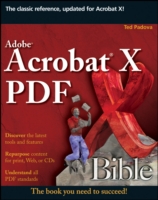出版社内容情報
貴重な図版満載の異色の文化史
氷原の上をよちよち歩くタキシード姿、好奇心いっぱいの「かわいい」やつ。大航海時代から「未知の大陸」のシンボルとしてさまざまな場面で大活躍してきたペンギンには、その一方で食料、燃料などとして利用されてきた受難の歴史もある。現代ではそのたくましさでも脚光を浴びつつあるペンギンから見た、貴重な図版満載の異色の文化史。
内容説明
人類とペンギンの過去・現在・未来。その愛らしさで世界中で絶大な人気を誇るペンギン。だが、過去には食料や燃料として大量に殺戮されてきた苦難の歴史もあった。過酷な環境の中で生き抜いてきたペンギンと人間の物語を斯界の第一人者が貴重な図版満載で紹介する文化史。図版60点以上追加で待望の復刊!
目次
序 人よせペンギン
第1章 太った海鳥
第2章 羽毛のはえた魚
第3章 ペンギンズ・イン・プリント
第4章 シロクマのともだち
第5章 オタクの国のペンギン踊り
第6章 ペンギンの現在地・人間の現在地
著者等紹介
上田一生[ウエダカズオキ]
ペンギン会議研究員、IUCN・SCC・ペンギン・スペシャリスト・グループ(PSG)メンバー。1954年、東京都出身。國學院大學卒業。ペンギン会議研究員としてペンギンの研究・保全活動を30年以上実施(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サンダーバード@読メ野鳥の会・怪鳥
63
(2024-98)【図書館本】動物園や水族館の人気者のペンギン。誰でも知っている野鳥の一種である。そのペンギンが過去からいかに世界各地で人間と関わってきたのか、色んな側面からみたペンギンの文化史。そもそもペンギンの語源ってラテン語のpinguis(肥満)によるという説があるとか。まあ確かにちょいメタボ。(笑)世界でも有数のペンギン好き国、日本で最初にペンギンを紹介したのはあの新井白石だったとか。内容は濃く、良い本ではあると思うけれど、私としては文化的な側面よりは生物学的な方が興味があるかな。★★★2024/07/25
アト
1
「ペンギンのしらべかた」がとても楽しかったので次は大容量のものをと。420ページくらいあった。最初からめちゃくちゃに狩られていてぎょっとしたがそりゃそうだよなと思い直す。食料として不可欠だった最初期はともかく、無闇に狩るのはおかしいと主張した人が出てきたときは安心した。どんなにかわいい生き物かではなく、人間から観測されたペンギンの本だった。発見された当初の伝聞には燕尾服を着た子供みたいだとあって表現がおもしろかった。博物館が標本欲しさに絶滅させた話はきっとしばらく頭に残る。→2024/12/21
与太
1
ペンギン好きを自認していて、よく水族館で眺めたりキャラクターグッズを買ったりしているので、歴史視点の本もおもしろそうだなとおもい手に取った。大航海時代の大量虐殺に心が痛み憤りなども感じていたけれど、近代現代と時代をたどるにつれ、南極=ペンギンの刷り込みやキャラクター消費に加担して、実際のペンギンの生態にほとんど興味を持ってなかった自分を自覚させられた 2024/08/20
474m4
0
創作においても象徴的な扱われ方のあるペンギンについて、たしかに私も興味を持っていたのですが、とりわけ日本が「ペンギン大国」というわけではないようです。この、ふくふくとした燕尾服の、よちよち歩きの海鳥からは、たまたま良質な油と肉が取れ、さらには、のろまで殺しやすく、おまけに、愛らしい容貌をしていたばかりに、人間とのあいだに不幸な縁が結ばれてしまった。我々はごめんなさいをしなければならないし、自然環境の歩哨たる彼らの危険信号を察知してこそ、たまたま知能の大きいヒトの面目躍如の機会だろう、という思いがあります。
三次元にある品川区
0
人類とペンギンの繋がりを事細かく書いたノンフィクション。 食料として、燃料として、毛皮として、南極探検の象徴として、西欧諸国の権威の象徴として、平和の象徴として、環境問題の代表例として、人間と深くクチバシをはさんで来てた生き物だった。 2025/03/09
-

- 電子書籍
- ワン・コンピュータームック 500円で…