出版社内容情報
もう一度、政治を好きになってみる。
「私は日本の民主主義の可能性を信じることを、自らの学問的信条としています。その信条はいささかも揺らぎません--」 稀代の政治学者が、現代の政治情勢に学問的立場から発言する。アメリカ、EU、中国、北朝鮮、香港、そして日本……。分極化する世界で、私たちに何ができるのか? 51篇の思索の軌跡。
内容説明
稀代の政治学者が、現代の政治情勢に学問的立場から発言する。アメリカ、EU、中国、北朝鮮、香港、そして日本…。分極化する世界で、私たちに何ができるのか?51篇の思索の軌跡。
目次
1 二〇一六年―「憂虜」(コモン・センスを問う;世界が分極化する中で ほか)
2 二〇一七年―「始動」(トランプの民主主義;米国の立憲主義 ほか)
3 二〇一八年―「予兆」(滑稽なネズミ;マクロンの徴兵制 ほか)
4 二〇一九年―「深化」(民主主義の最後の砦;奇妙な中ぶらりん ほか)
5 二〇二〇年―「異変」(劇的事件に慣れる怖さ;危機に備える哲学 ほか)
著者等紹介
宇野重規[ウノシゲキ]
1967年東京都生まれ。政治学者。東京大学法学部卒業。同大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。専門は政治思想史、政治哲学。千葉大学法学部助教授、フランス社会科学高等研究院客員研究員を経て、現在、東京大学社会科学研究所教授・副所長。『政治哲学へ―現代フランスとの対話』(東京大学出版会)で2005年度渋沢・クローデル賞ルイ・ヴィトン特別賞を、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社選書メチエ)で2007年度サントリー学芸賞(思想・歴史部門)をそれぞれ受賞。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
jackbdc
hiroshi
めぐりん
てぷてぷ
-

- 電子書籍
- VOGUE JAPAN 2025 3月号
-

- 電子書籍
- 魔王になったので、ダンジョン造って人外…
-

- 電子書籍
- バロン(分冊版) 【第42話】 ぶんか…
-
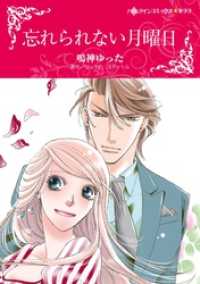
- 電子書籍
- 忘れられない月曜日【分冊】 2巻 ハー…
-

- DVD
- 賃走談 1号車




