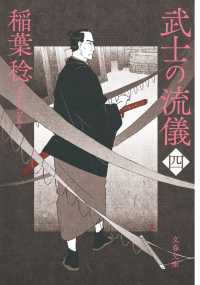内容説明
STAP細胞騒動は、現代科学がきわめて重大な問題に直面していることを明るみに出した。いま科学は実利と倫理の間で引き裂かれ、本来のありようから大きく逸脱しているのではないか?長年、生命倫理の研究と政策論議に携わってきた著者が、科学の必要性と妥当性に立ち返り、根底から立て直すための道筋を示す基本の書。
目次
序章 STAP細胞問題から考える科学と社会の関わり方
第1章 研究倫理の基本―科学する欲望にどう向き合うか
第2章 生命倫理とは何か―日本のこれまでの歩みと今後の課題
第3章 研究倫理の応用問題―再生医学、人工生命研究から宇宙での研究まで
結章 生命の科学の拠りどころ―成熟への道筋
付論1 生命科学と生命倫理のもう一つの接点―脳死論議と生命観の基礎としての免疫学再考
付論2 人間の欲望を軸にした臨床医学論の構想
著者等紹介
〓島次郎[ヌデシマジロウ]
1960年生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程修了、博士学位取得(社会学博士)。三菱化成(現「化学」)生命科学研究所、科学技術文明研究所主任研究員などを経て、2007年より、東京財団研究員(非常勤)。自治医科大学客員研究員。参議院厚生労働委員会にて臓器移植法改正案審議・参考人意見陳述(2009年7月6日)など政策立案の議論にも携わる。専門:生命科学・医学の研究と臨床応用を中心にした、科学政策論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
29
間違うのは科学の本質の一つ。仮説が証明できるか研究を続けるのが科学者の責任の取り方 (13頁)。科学者は、科学する欲望の充足を生業としている存在(15頁)。研究倫理とは、科学する 抑制の原理(35頁~)。STAP問題で問われることになった科学者倫理だが、根深い問題を孕む。 過剰な競争、業績主義にも問題があると思う。 2015/05/15
かーんたや
1
齢50を過ぎてよくこんな主観的な本だしたな これ含め税金出す価値なし2019/08/09
たみす
0
科学する欲望と、普通の名誉やお金を求める欲望を分けて、科学は前者の、物事を解き明かそうという欲求にしたがって運営されるべきだって本なんだけど、目線は科学者的でもないし、ジャーナリスト的でもないし、法哲学者って感じでもなく、なんかふわふわした素人の意見って感じ。 たとえば、理化学研究所に既得権益やお金のため名誉のため所属する輩がいるというような論調にしたって、こうした特別扱いは、科学する欲望を満たすのにじゅうぶんな設備や資金という意味で大事だと思うし、必ずしも世の中の人みんなが役に立たない科学にお金を出すこ2016/06/11
-

- 洋書
- Meme's Farm
-
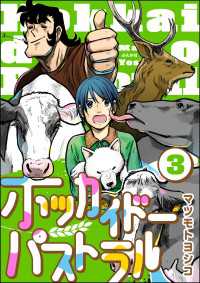
- 電子書籍
- ホッカイドーパストラル(分冊版) 【第…