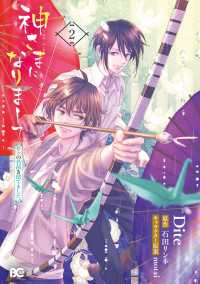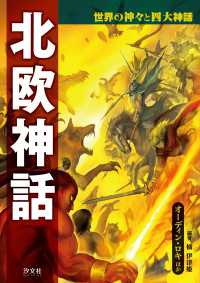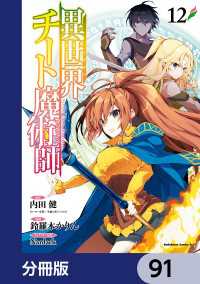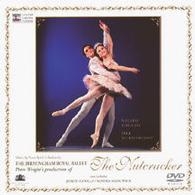内容説明
ネオリベラリズムから教育、サブカルチャーまでを、現代社会に「生きる人びと」に寄り添いながら分析。ラカン派精神分析を用いた「臨床社会学」による現代社会へのアプローチ。
目次
1 基礎
2 理論(ポストモダン的「民意」への欲望と消費―転移空間としてのテレビにおいて上演される「現実的=政治的なもの」;「資本主義の言説」(ラカン)と「新しい心理経済」(メルマン)
現代社会における構築主義の困難
ジェンダーと現代の精神分析
ポストモダンにおけるメランコリーと倒錯)
3 実践(「リアリティショー」の社会学的分析;脱文化化と移行のない「移行空間」―宗教の脱文化化(「無知聖人」)と若者の「teuf」(飲んで騒ぐこと)の事例に見る
ケアの社会学的考察
フィンランドモデルを超えるために―「境界地」/教師の欲望/ヴィゴツキー的「現実界」
教育の心理学化―あるいはm´ediationとしての幻想と転移の倫理学)
著者等紹介
樫村愛子[カシムラアイコ]
1958年京都生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科社会学専攻博士課程満期退学。現在、愛知大学文学部人文社会学科教授。専門はラカン派精神分析の枠組みによる現代社会・文化分析(社会学・精神分析)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。