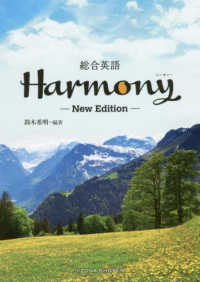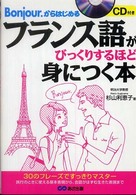内容説明
超国家的“帝国”を担いながら、偏狭なナショナリズムに陥るアメリカ。気鋭の社会学者が、「9・11」前夜の滞米経験をふまえ、その変貌のメカニズムを摘出し、同じ病理を別の形で抱えた日本社会の危機と未来を展望する。
目次
1 日本の変容(なぜオウムの存在はかくも耐えがたいのか?;少年の殺人と電子メディア ほか)
2 アメリカの変容(司法的精神の逆説―大統領の不倫;寛容と不寛容―コロンバイン高校銃撃事件 ほか)
3 現代社会の変容(加速資本主義論―ディズニーランドと世界の内外;エアポート論―「都市」以後の「ネーション」(多木浩二/大沢真幸))
4 日本とアメリカの現在(帝国的ナショナリズム)
著者等紹介
大沢真幸[オオサワマサチ]
1958年、松本市生まれ。比較社会学、社会システム論。1990年、東京大学大学院社会学研究科博士課程博士号取得。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
37
00年前後の時評を集めた論集で、他の本で書いていた理論的な枠組みを別の言葉で言い換えていることが多いので、トピックの関心よりも著者の仕事に関心があり、さらに読んでいきたい人向けの本です。多重人格は多重が問題なのではなく、多重を統合することが出来ないことが問題なのである。「糊代」を持たない多重人格化が、人格がひとつしかない人に起これば離人症になると非常に鋭い指摘があります。著者が平野啓一郎の「分人」に冷淡なのも得心し、「糊代」は固有名であるというのが著者の考えだろうと思います。2022/05/22
ひつまぶし
2
ある本の孫引きで気になることが書かれていたので読んでみた。しかし、内容は少し歪められて引用されているっぽい印象を受けた。基本的には当時の著者が書いた評論の寄せ集めで、文体に比して内容はさほど難しくはなかった。やはりどこか精神分析的なスタンスを採用した世界の読み解き方は、しかし著者が臨床的な場を欠いているという意味で重みがない。一見世界と向き合っているようで、具体的に解決しなければならない切実な課題を欠いた空想という感じがする。視点だけで思考すれば量産はできるだろうが、それゆえにその程度のものでしかない。2023/07/07