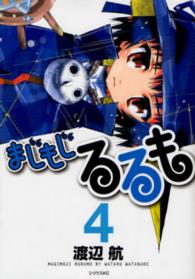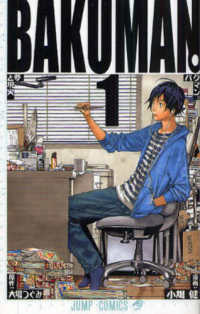内容説明
猿の集団が大きくなって「毛づくろい」ができなくなったとき、それに代わるコミュニケーション手段として生まれたのが人間の「ゴシップ=言語」だった―生物学、脳生理学、人類学、心理学などの最新成果を踏まえ500万年を鳥瞰し、ことばの進化の歴史を根底から覆す。
目次
1 むだ話をする人々
2 めまぐるしい社会生活へ
3 誠実になることの重要性
4 脳、群れ、進化
5 機械の中の幽霊
6 はるか彼方へ時をさかのぼる
7 最初の言葉
8 バベルの遺物
9 生活のちょっとした儀式
10 進化の傷跡
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
さな
2
人類学者である著者が、人類がなぜ言葉を使うようになったのかを論じた一冊。著者は、霊長類が対応可能な社会的つながりが150人以下であること、また、群れの規模拡大より猿の時代の毛づくろいでは時間が足りなくなり、社会的なつながりを維持するために言葉が生まれ、進化してきたことを述べており、現代の仮説として非常に面白く専門外の私にも読みやすい。また本書(98年刊)では、話し手と聞き手が60センチ以上離れたり、会話人数が4人を超えると話が伝わりづらくなることにも言及されており、いまのウィズコロナ時代に考えさせられる。2020/06/27
田中はにわ
2
「サピエンス全史」で引用されている本。自然選択、進化と代償、生存・繁殖、脳内麻薬、毛づくろい→言語、あたりがキーワードか。2017/12/17
メロン泥棒
2
原著は1996年刊。人間社会の成り立ちと「言葉」について示唆に富む傑作中の傑作。霊長類では大脳皮質の体積と群れの大きさは比例しており、人間では150人が正当な群れの大きさとなる。猿は毛繕いにより結束を固めているが、150人で毛繕いするのは効率が悪いため、人間は「言葉」で結束を固めている。この150人説と言葉の持つ意味から、会社や都市での人間関係、さらにはネットを通じたコミュニケーションの可能性など多彩な話題へと広がる。10年以上前の本だが色あせない。むしろネットが反映している今だからこそ読みたい1冊。2010/10/24
diet8
0
群れの規模を維持するために猿はかなりの時間を毛づくろいに費やす。群れの数は約50。現生人類はゴシップを話す。一対一でなく、四人組くらいで話せる。よって、群れの規模は150人ほどとなる、脳の新皮質の大きさからもこの数は出る。人は消化器官へのエネルギー消費を抑え、肉を食うことで、エネルギーを食う脳を巨大化させた。右利きと右脳の話。紀元前13000年前の言語ノストラチック。言語が変化するのはフリーライダー対策として出身の印とするため。2015/10/05
-

- 和書
- 私の國語教室 文春文庫