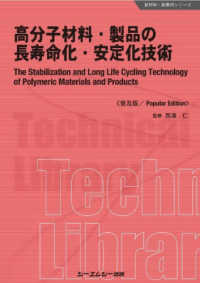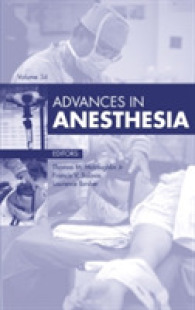内容説明
なぜ彼らは旅人であり続けるのか?都市周辺の空き地に移動式住居(キャラヴァン)をとめて暮らすフランスのマヌーシュ。“住まう”という社会的かつ身体的な実践を通して、社会変化と他者の只中で共同性を紡ぐ人々の姿を描きだす。
目次
ジプシーの住まいと共同性をめぐって
第1部 旅の道具としてのキャラヴァン―定住化の時代における共同体と移動生活(変動するマヌーシュ共同体;行き詰まるキャラヴァン居住;定住化の時代におけるノマディズムの再編)
第2部 居住の道具としてのキャラヴァン―身体、他者、環境との関係(“外”へと開かれる住まいと身体;身体を包み、位置づけるキャラヴァン;キャラヴァンが支える沈黙の共同性)
紡がれる“私たち”とその居場所
著者等紹介
左地亮子[サチリョウコ]
1980年京都府生まれ。筑波大学大学院博士課程人文社会科学研究科修了。博士(学術)。現在、日本学術振興会特別研究員PD(京都大学)。専門は、文化人類学、ジプシー/ロマ研究。2013「空間をつくりあげる身体―フランスに暮らす移動生活者マヌーシュのキャラヴァン居住と身構えに関する考察」『文化人類学』78(2)で日本文化人類学会奨励賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
6
松井梓さんきっかけ。終章にある「旅する人々の創造的な居場所構築」P252という言葉が本書の核心を表わしているのですが、先行研究に関する言及の中に左地さん自身の言いたいことが埋没してしまっていてちょっと読みにくい印象でした。自己と状況の相互作用に注目しつつ、能動的に「住まうこと」を作り出す自己を見いだすことで、個人と共同体の、現存在と世界との二元論を乗り越えたいという意図みたいなんですが・・・その先が良く分かりませんでした。2025/05/24
takao
0
ふむ2025/08/08
はしも
0
定住民には無縁だった移動民族の世界。はじめて民族誌を読んだが、フィールドワークの基盤になる膨大な先行研究のレビューや社会理論など、文化人類学の大変さと奥の深さも学べた。2018/07/10
-

- 電子書籍
- 新郎新婦ご入場です! 素敵なロマンス
-

- 和書
- 西行自歌合全釈