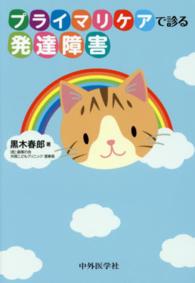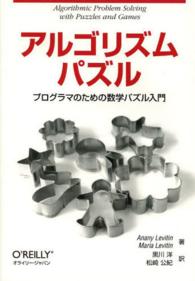内容説明
仕事・社会・コミュニケーション・宗教・異文化の5ジャンルを網羅し、40人の初々しいフィールドワークを一挙公開。技術的なノウハウから理論的な設問まで、実践的な助言を満載。フィールドワーカーのセンスを体得できる最良の指南書。
目次
他者と出会う
第1部 「謎」と出会う通路(仕事の世界;社会とその周縁;コミュニケーションの内と外―疎通・伝播・伝承;信じることの手ざわり;「外国人/異文化」との遭遇)
第2部 「謎」をひもとく(“振売り”都市に息づく野菜行商;棚田を“守り”する人びと―伝統的棚田の保全と開発;生きものを屠って肉を食べる―私たちの肉食を再考する試み;摂食障害に立ち向かう女たち;銭湯の行動学;エチオピアのビデオ小屋)
生きかたとしてのフィールドワーク
著者等紹介
菅原和孝[スガワラカズヨシ]
1949年東京生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科教授。同総合人間学部で人類学関係の全学共通科目を開講し、フィールドワーク(調査演習)の授業をもっている。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。霊長類(ニホンザル、ヒヒ類)の社会行動研究から出発し、1982年より、南部アフリカのボツワナに住むグイ・ブッシュマンの社会で、身体的な関わり、会話、語り、動物認識などをテーマにフィールドワークを続けている。並行して、日本人の会話と身ぶり、民俗芸能の伝承などについて研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のぎへん
9
"人生至る所フィールドあり"…人類学の入門書。フィールドワークの主な手法として、あるコミュニティに観察者自身が入り込み能動的かつ受動的に観察する「参与観察」というものがある。参与観察では、観察対象の「他者」だけでなく、それを理解していく自己が論文の登場人物として大きな存在となりうる。ともすれば無味乾燥になりがちな論文が、その人にしか書けないひとつの物語になるのだ。人類学なんて仰々しいもの興味ないよ、なんて人にこそオススメしたい一冊。2016/04/28
おかおか
3
課題図書。こんな風な卒論書ける日がくるといいな。2016/04/08
湯飲み猫
3
フィールドワークへの心構えを軸にして、学生の調査報告を具体的な例として解説していく本書。フィールドワークは門外漢な私ですが、とても興味深く読めました。学問であるため客観性は必要だけど、同時に、調査する者がひとりの人間として何を学び、何を得たのかを重視するのが、人の営みを調査するうえでとても大切なのですね。後半の論文集も面白かった!2014/05/27
★★★★★
3
京大人類学の菅原先生による一風変わったフィールドワーク入門。学部の調査実習で提出されたレポートを引用して厳しく論評しつつ、初心者が直面する問題を明らかにしてゆく第Ⅰ部と、6人の元教え子たちが書き下ろした論文を収める第Ⅱ部からなっています。身近なテーマが多くて読み物としても面白いですし、いろいろ思い当たるフシもあって大変参考になりました。それにしても京大の学生は優秀だなぁ。2010/03/22
kakari
1
『銭湯の行動学』、何度読んでも著者の熱意、センス、データの緻密さに脱帽する…すごい!2024/08/26