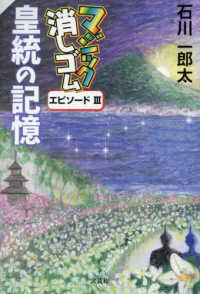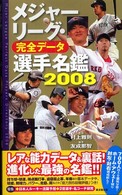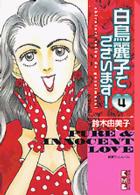内容説明
ポストコロニアリズムが浸透し人類学者による人類学批判がはじまった1980年代以降、領域を広げつつも、方途を失ったかに見える人類学、その倫理と政治を問い、枠組と理論を再考する。
目次
序論 ポストコロニアル転回後の人類学的実践
第1部 人類学的実践の倫理と政治(「文化の翻訳」の流通・消費の側面―「ファンダメンタリズム」と「原理主義」をめぐって;異文化理解の倫理にむけて;紛争研究と人類学の可能性;文化/人類学―文化解体を超えて;人類学の正義と正義の人類学 ほか)
第2部 人類学的実践の枠組と理論(対比する語りの誤謬―キドゥルマと神秘的制裁;人類学の設計主義;儀礼の受難;非同一性による共同性へ/において;越境から、境界の再領土化へ―生活の場での「顔」のみえる想像 ほか)
著者等紹介
杉島敬志[スギシマタカシ]
1953年生まれ。東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程修了。博士(文学)。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授。専攻は人類学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
★★★★★
4
1980年代における人類学批判によって人類学が陥った他者表象をめぐる閉塞状況を「ポストコロニアル転回」と捉え、それ以後の学問的実践のあり方について考察した論集。どこかで聞いた話も多かったけど、これはなかなか参考になりました。面白いと思ったのは、『文化を書く』に言及している論者はみなその重要性を認めつつも、提示される記述のあり方については一様に批判的なこと。考えてみると確かに、日本語の優れた実験民族誌って聞いたことないかも。所詮は西欧的自我を前提としたエクスキューズに過ぎないってことなんですかね。2010/08/24
-
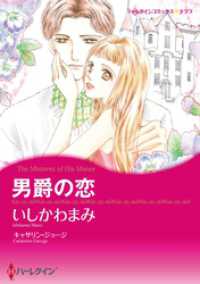
- 電子書籍
- 男爵の恋【分冊】 5巻 ハーレクインコ…
-
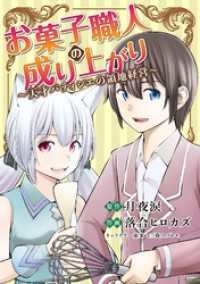
- 電子書籍
- お菓子職人の成り上がり~天才パティシエ…