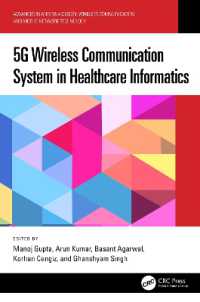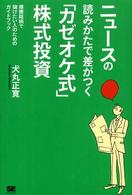出版社内容情報
2021年7月初めから急速に患者が拡大し、9月まで続いた新型コロナウイルスの感染拡大第5波は、それまでにない激流となって各地に押し寄せた。重症化する患者が相次ぎ、入院が必要なのに在宅での療養をよぎなくされる患者も激増。入院できないまま自宅で死亡する例も出た。もはや「医療逼迫」を超えて「医療崩壊」と言わざるをえない惨状を呈した。
東京都では、8月12日~9月14日の間、都の基準による重症者数が連日200人を超え、8月28日には過去最高の297人に達した。重症者用の病床使用率は、9月1日に96.9%となった。
救急車を呼んでも、搬送先がなかなか見つからず、長時間患者が車内で待たされるケースも増加した。救急隊が「医療機関への受入れ照会」を4回以上おこない、「現場滞在時間」30分以上に及んだ「救急搬送困難事案」を、総務省がまとめているが、東京都では7月19日から9月12日までに毎週1000件以上が報告されている。とりわけ8月9日~15日の週においては、その数は1837件にも上った(うち、コロナ疑いは870件)。
自宅療養者の死亡者も同様に増加し、9月19日付読売新聞によると、8月1日以降9月17日までの東京都で、自宅療養中に亡くなった人は44人(救急搬送後の死亡者を含む)を数えた。
そんな中、東京都墨田区のデータがひときわ目を引く。
同保健所によると6月25日~9月29日の重症者数はゼロ。大都市圏でこの時期に重症者が1人も出なかった自治体は珍しいのではないだろうか。入院待機者も8月中旬にはゼロとなり、ほかの都市部の自治体のように、本来入院が必要な患者が自宅療養をよぎなくされる、という事態はなくなった。
こうした対策が功を奏した背景には、速やかなワクチン接種や、「墨田区モデル」とも呼ばれる地域内で完結する医療体制の整備、区と医療関係者の連携、議会の対応など、いくつもの要因がある。
本書では、そうした墨田区の対策を概覧しながら、なぜワクチン接種を速く進めることができたのか、ワクチン以外にどのような対策が有効だったのかを見ていくことにする。墨田区の取り組みと知見を記録として残すことで、危機時における地方自治体のあり方を考える参考にしていただければ、と思う。
内容説明
次の「波」を想定し、先手で対応した保健所長。災害に備え地道に訓練を重ねてきた医療・行政関係者。密かにPCRの技術を磨いてきた検査技師。ワクチン接種で協力し合う地元住民たち…。「奇跡」を「必然」に変えた偉業の陰には、多くの立役者がいた!
目次
序 奇跡の重症者ゼロはなぜ可能だったのか
第1章 ワクチン接種(試行錯誤のスタート;「わく丸」誕生;墨田区が迅速にワクチン接種をできた理由;供給不足のワクチンをどのように確保したのか)
第2章 行政と医療の連携(「人が大事」―自前でPCR検査体制を整えた保健所;住民に必要な情報を公開し、発信する;「オール墨田」を築いた週1のWeb会議;「墨田区モデル」;大車輪の活躍を見せた訪問看護師たち;第5波への備え;困難な妊婦を受け入れる)
第3章 想定外との戦い(失敗から学ぶ;議会改革の成果;「想定外」まで想定して次の「波」に備える)
第4章 地域の力(地域が力を発揮するためには何が必要か;過去の災害対応の反省を土台にする)
著者等紹介
江川紹子[エガワショウコ]
1958年生まれ。ジャーナリスト。神奈川新聞記者を経て1987年よりフリーランス。関心分野は司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など様々。1995年にオウム真理教報道で菊池寛賞を受賞。2020年4月から神奈川大学国際日本学部特任教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。