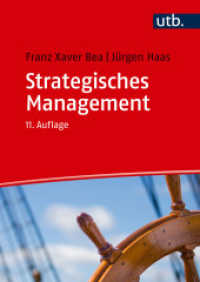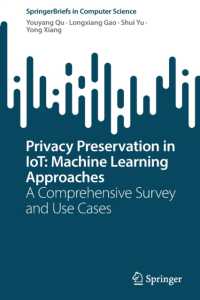出版社内容情報
過去の史資料を集めるだけでは、歴史の社会学として許されない。それらをもとに、「歴史」をひとつの物語として立ち上がらせることが、社会学として意識されねばならない。
今ここに存在しない「歴史」を現前にたぐり寄せ、その多面性を描き出す想像力こそが、実証と向かいあう歴史社会学を前にすすめる動力である――この方法論を共有する著者たちが多様な歴史テーマに挑んだ、オリジナルな研究のフォーラム。
内容説明
歴史社会学を「社会学」たらしめるのは、いまここに存在しないものへの想像力である。記録や資料、データを集めて記述するだけでは足りない。素材をもとに、私たちの眼前にひとつの物語として「歴史」を呼び起こすとき、社会学が立ちあがる。実証と向かい合いつつも、素朴な実証主義に陥らない、歴史社会学の挑戦。
目次
第1章 文書館の政治学―“啓蒙の装置”から“記憶の装置”へ
第2章 トラウマの言説史―近代日本は「心の傷」をいかに理解してきたか
第3章 南ティロルにおけるファシズム/レジスタンスの記憶―解放記念日と凱旋門の顕彰を手がかりとして
第4章 戦争体験と「経験」―語り部のライフヒストリー研究のために
第5章 日本社会論の現在と戦争研究の社会学的可能性
第6章 丸山真男の歴史社会学―遙かなる過去から東アジアの近代を見るとき
第7章 昭和五十年代を探して
第8章 戦前日本における家族社会学前史―『社会学研究室の一〇〇年』を手がかりとして
第9章 コミュニティを統治する―ハウジングの社会調査史
第10章 歴史社会学の作法の凄み―『流言蜚語』について
著者等紹介
赤川学[アカガワマナブ]
1967年生まれ。石川県出身。東京大学大学院人文社会系研究科社会学専攻博士課程修了。博士(社会学)。現在、東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門はセクシュアリティ研究、言説社会学。今後は猫社会学の確立を目指す
祐成保志[スケナリヤスシ]
1974年、大阪府生まれ。2005年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会学)。信州大学人文学部准教授などを経て、2012年より東京大学大学院人文社会系研究科准教授。関心領域:ハウジング、コミュニティ、社会調査史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。