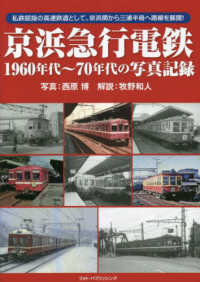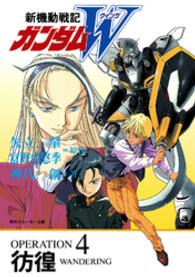内容説明
近代日本が西洋芸術の受容と普及に努める過程で、音楽は静かに「きく」べきもの、「わかる」べきもの―“鑑賞”するもの―となった。文化に深く埋め込まれ、音楽を超えて芸術に対する私たちの態度のなかに今も息づく、“鑑賞”の誕生と変遷の文化史。
目次
序章 日本にだけある“鑑賞”という言葉
1章 音楽をきくのは専門家―明治の“鑑賞”は批評?
2章 子どももみんな音楽をきこう―信じられた芸術鑑賞の力
3章 音楽をきいて精神訓練―クラシック音楽の“鑑賞”で身につける日本精神?
4章 音楽を愛そう―日本国民は将来みんなクラシック音楽鑑賞者
5章 音楽は「ただきく」ものではない―“鑑賞”と「きく」ことの違い
6章 みんなできこうクラシック音楽―“鑑賞”は日本人の義務
7章 ポピュラー音楽にかなわないクラシック音楽―“鑑賞”教育の失敗
終章 なぜ日本にだけ“鑑賞”という言葉が生まれたのか
著者等紹介
西島千尋[ニシジマチヒロ]
1981年生まれ。2009年金沢大学大学院人間社会環境研究科博士後期課程修了。博士号(学術)取得。学位論文で人間社会環境研究科長賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Taka
35
西洋列強に文化の面でも追いつこうとする流れが書かれてるのかな。音楽ひとつ取っても国の方針として定めていくにはやはり承認を得るための理屈は必要なんですね。なるほどーって感じです。2018/01/23
tegege
1
音楽評論でなく、鑑賞への歴史的推移を日本教育の観点から述べた本。丁寧な論文だが文献をなぞった感が否めない。音楽評論の観点では、ちょっと物足りない。2013/04/28
moco*
1
序章と終章はなかなか面白い。2011/08/25
momo komatsu
0
話が現在に近づいて来ると読んでて本当に苦しくなってくる。今後音楽家は何ができるのだろうか2012/07/27
-

- 和書
- 英語で味わう日本の文学