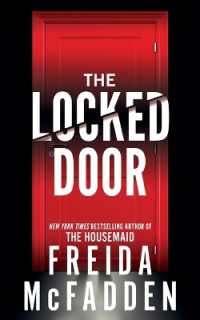目次
笑話本研究序説
1 幕末期の笑話本
2 三題噺とはなにか―三笑亭可楽の三題噺
3 三題噺の復活―三題噺の会誕生
4 『粹興奇人傳』の人たち―同人組織のつながり
5 河竹其水の三題噺―歌舞伎と落語の創作
6 三遊亭円朝の三題噺―作家への基盤をつくる
7 其水作の三題噺「鰍沢」を読む―三題噺から落語へ
付 『春色三題噺二編』と『圓朝全集』の本文校勘
著者等紹介
宮尾與男[ミヤオヨシオ]
1948年11月、東京都北区王子に生まれる。1976年3月、日本大学大学院文学研究科国文学専攻博士課程単位取得満期退学。武蔵野女子短期大学部、大東文化大学文学部、日本大学文理学部、同医学部、同理工学部講師を経て玉川学園女子短期大学専任講師。その後、玉川大学文学部、同通信教育部、日本大学文理学部、同理工学部、同短大部、同芸術学部、同通信教育部講師を歴任。日本近世文学会委員、全国国語国文学会編集委員、国文学研究資料館共同研究員、日本人形玩具学会委員、民俗芸能学会理事、国立劇場公演専門委員。専攻/学位 近世文学・近世文化/文学修士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
1
幕末期の笑話本:笑話本 風刺文化 幕末落語 三題噺 可楽の影響 其水の劇化 円朝の創作 口承文学の発展 江戸と上方の違い 三題噺の発展:即興話術 聴衆参加 笑話の多様化 口演の発展 落語との融合 物語の脚色 三題噺の会 口語表現の工夫 文化資本の蓄積 笑話:社会批判 大衆娯楽 文学への影響 口承文学の継承 風刺の深化 笑いの変遷 民衆意識の反映 庶民文化の形成 時代背景の映写 幕末から明治へ:口語表現の発展 文芸の変革 演劇との融合 近代落語の基盤 新たな話芸 話芸の継承 活字文化の拡大 近代文学への影響2025/03/06
Go Extreme
1
笑話本研究序説: 笑い話から笑話へ 笑話本の誕生・世界・文学・流れ 幕末期の笑話本: 林屋正蔵の存在 笑話本と落語 心を癒す喜びをもとめる 三題噺とはなにか―三笑亭可楽の三題噺: 即興話の流行 誤謬の記述 即興と即席 三題噺の復活―三題噺の会誕生: 採菊催主の会 三題噺同人作品集 報条摺物 双六にみる兼題 粹興奇人傳の人たち―同人組織のつながり 河竹其水の三題噺―歌舞伎と落語の創作 三遊亭円朝の三題噺―作家への基盤をつくる 其水作の三題噺「鰍沢」を読む―三題噺から落語へ 春色三題噺二編と圓朝全集の本文校勘2024/12/27