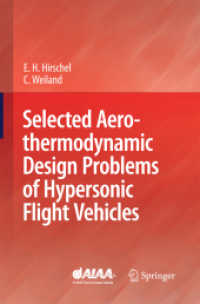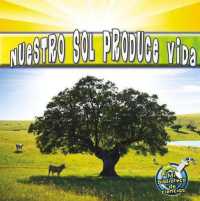内容説明
「責任ある生産と消費」の裏側で起こっていること―。私たちの日用品であるトイレットペーパーやパーム油。環境や持続可能性への配慮を謳った製品が流通するなかで、原産地インドネシアでは何が起こっているのか。熱帯林開発の現場に生きる人びとが直面しているさまざまな問題を見つめ、「熱帯林ガバナンス」のあるべき姿を考える。
目次
現場から考える「熱帯林ガバナンス」のあり方―周縁化された「草の根のアクター」の視点から
1 誰のための「熱帯林ガバナンス」か(力を持つアクターたちがつくり出す「現実」とかき消される声―APP社「森林保護方針」に基づく自主規制型ガバナンスの事例;持続可能な森林経営をめぐるポリティクス―複雑化する現代社会で「人と人の信頼」は再構築できるか)
2 認証制度が現場にもたらしたもの(パーム油認証ラベルの裏側―文脈なき「正しさ」が現場にもたらす悪い化学反応;大規模アブラヤシ農園のRSPO認証取得と取り残された労働者たち)
3 「住民の同意」とは何か(インドネシア最大手の製紙会社による「紛争解決」と「住民の同意」;「住民との同意」は本来の目的を果たせるのか)
4 土地支配の強化のなかで生きる営みが「違法」とされていく人びと(人びとはなぜ「不法占拠者」になったのか―強制排除された人びとの生活再建に対する社会的責任;カンパール半島における土地支配の強化と再生産される「違法伐採」)
著者等紹介
笹岡正俊[ササオカマサトシ]
東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程単位取得退学。博士(農学)。北海道大学大学院文学研究院准教授。専門は環境社会学、ポリティカルエコロジー
藤原敬大[フジワラタカヒロ]
九州大学大学院生物資源環境科学府森林資源科学専攻博士後期課程修了。博士(農学)。九州大学大学院農学研究院准教授。専門は森林政策学、林業経済学、ポリティカル・フォレスト論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
makimakimasa
Hiroo Shimoda
Y.Yokota
Go Extreme
-
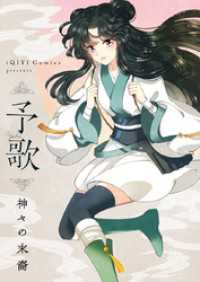
- 電子書籍
- 予歌~神々の末裔~【タテヨミ】第6話 …
-
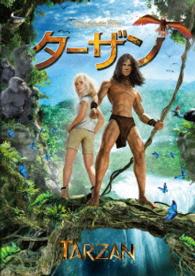
- DVD
- ターザン