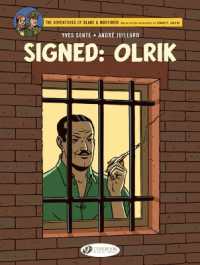内容説明
琉球王国の政治・経済・文化の中心的役割をはたしてきた城、首里城。戦後、沖縄戦で破壊された正殿の復元が叫ばれるなか、その真の姿を発掘調査によって追究してきた著者が、沖縄を代表するグスクとしての首里城の特色と出土した貿易陶磁器、装飾品などを解説する。
目次
第1章 首里城をとり戻せ(沖縄戦と首里城;首里城を復元せよ;よみがえる首里城)
第2章 グスクの時代(先史時代の琉球;グスクの誕生;大交易時代;グスク時代の発展;三山分立から統一へ)
第3章 琉球王国の象徴・首里城(首里城を鳥瞰する;伊東忠太・鎌倉芳太郎らの調査;正殿の発掘;正殿の遺物;北殿と南殿;京の内跡;精巧優美な石垣)
第4章 琉球王国の終焉と首里城(琉球王国の終焉;世界遺産になった首里城跡とグスク群;復元正殿焼失とこれから)
著者等紹介
當眞嗣一[トウマシイチ]
1944年、沖縄県西原町生まれ。琉球大学法文学部史学科卒業。沖縄県教育庁文化課課長、沖縄県立博物館館長、沖縄考古学会会長を歴任。現在、グスク研究所主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鯖
19
首里城を通じて沖縄の歴史を知る本。江戸時代に3度、米軍による空襲、先年の失火と5度焼けた首里城。やっぱり焼けるんだよなあ…。再建の道は険しそうですが、思い入れのある方々になるべく納得できる形で落ち着くといいなあ。種子島に鉄砲が伝わる100年以上前に、その首里城に火器使用の跡が存在し、首里城にも鉄砲狭間に、石ではあるが弾丸の製作所の跡があるというのに驚いた。蒙古のてつはうじゃないけども、大陸文化が色濃い土地なんだなあと思う。…島津にてつはうガンガンぶん投げてたらなあと思ってしまった。2020/10/03
もるーのれ
4
首里城の歴史と構造がよく分かる1冊。石垣などの城郭の構造や出土した陶磁器・火器などは、本土とはだいぶ様相が違う。本当に異国なんだなぁと興味深い。また、正殿などの復元建造物は失火によって消失してしまったのは残念な限り。時間はかかるだろうけど、しっかりした考証に基づいて、再度復元された姿を見てみたい。2020/06/28
ヒトコ
2
若い頃から日本の歴史に興味はあったが、それは中央の歴史。 沖縄の歴史を詳しくは知らないが、沖縄県になる以前は琉球王国だった事は知られている。 本書では古代からグスク時代を経て琉球王国が成立するまでの流れがザックリとわかる。その政権の中心であったのが、タイトル通り首里城だ。 他のグスクとの比較や地形図による立地の解説、発掘調査で出土した周辺諸国産の品々なども興味深かった。2024/10/29
kaz
2
タイトルどおり、首里城の歴史等を紹介。種子島への鉄砲伝来よりも前に沖縄に火器があった可能性があるというのは驚き。歴史が、また塗り替えられるかもしれない。戦争、戦後の大学設置、今回の火災等々、歴をを残すという点で、これまで大きな苦難を強いられてきた城。今後の復元がどうなるのか、注目される。 2020/06/10
takao
0
ふむ2025/10/10