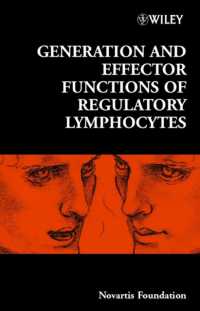- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
千円札一枚で酔える=「千ベロ」で有名な京成線立石駅前、仲見世の飲み屋街。なぜ立石は千ベロの聖地になったのか?東京下町の飲みスタイル(流儀)とはどんなものか?「宇ち多゛」「みつわ」「江戸っ子」の魅力はどこにあるのか?京成押上線沿線の歴史と文化を掘り起こしつづける著者が熱く語る。
目次
1 思い出の中のもつ焼き屋さん
2 下町ハイボールともつ料理
3 立石のもつ焼き屋さん細見
4 立石仲見世物語
5 京成押上線と千ベロの聖地誕生
6 立石の地霊
付章 立石にあった「つたや京染店」
著者等紹介
谷口榮[タニグチサカエ]
1961年、東京都葛飾区生まれ。国士館大学文学部史学地理学科卒、博士(歴史学 駒澤大学)。立正大学・明治大学・國學院大學・和洋女子大学兼任講師、NHK高校講座日本史講師歴任。現在、葛飾区産業観光部観光課主査学芸員。よみうりカルチャー講師、新潮講座講師も務めている。(立石三郎、勝鹿亭立石というペンネームでも執筆活動をしている)日本考古学協会理事、観光考古学会理事、日本歴史学協会文化保護特別委員、境界協会顧問など。研究テーマは、東京下町や旧葛飾郡域の環境と人間活動の変遷を通史的に研究、そのほか地形や地理と人間活動の関係性、地域的な飲食文化なども調査研究対象としている。著作多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しんさん
6
京成立石の名店たちが再開発でなくなってしまう・・・ので読んでみた。その2 立石育ちの著者の本業は考古学者。各店のお皿を土器のように図解してみたり、詳細な間取り図をつくってみたり。各店の名物料理、お作法、雰囲気、匂いまで「今の立石を歴史に残そう」という強い思いが感られて泣ける。最高。 街の歴史も詳しくかかれており、地名のもととなった石は、古墳の石室の石材だったものが平安時代に道しるべとして再利用され、現在は「立石様」として祀られているとか。もうなんだか、今すぐ立石で飲んだくれたくなってくる一冊。良本! 2022/03/10
侍の笛1吋
1
図書館で見かけた本 呑み仲間と立石探索を行う予定でしたが、コロナ禍で中断してます。 立石の再開発が進む前に、焼き 煮込み 刺しとボールで2021/06/05
snzkhrak
0
日経で見て、ヒストリカルブランディングからの繋がりで選書。考古学者による立石の地域文化の考現学的記録。再開発予定の街を悼む書でありながら、著者の言うように街の未来の手掛かりの書であるし、そうあって欲しい。各店舗はこれからどうするのか、地域文脈は誰がどう引き継ぐのか、ある店は後継店ができたようだし、またある店は再開発ビルに入るようだ。今の日常に注意を払うべきだし、さらに言えばこれからの未来に関心を向けるべき。曳舟は街の個性たる、歴史の重なりを感じさせる記憶装置が無くなってしまったとの事だが、それでは寂しい。2024/02/11
-
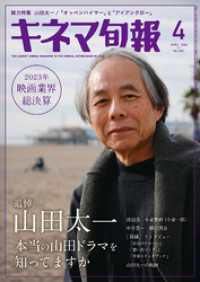
- 電子書籍
- キネマ旬報 2024年4月号
-
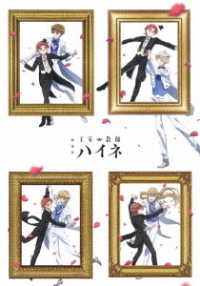
- DVD
- 劇場版「王室教師ハイネ」DVD