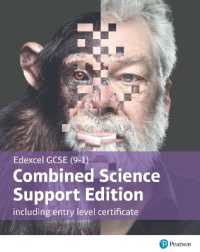内容説明
東京の街にいまだ江戸の面影が残る一八七二年(明治五)の秋、一台の蒸気機関車が文明開化の夢をのせ、汽笛を鳴らしプラットホームを滑りだした。近代日本の玄関口として多くの人びとが旅立った新橋ステーションの姿を発掘された鉄道関連遺構・遺物から描きだす。
目次
第1章 鉄道考古学事始
第2章 はじめての鉄道建設
第3章 姿をあらわした新橋停車場
第4章 汽笛一声
第5章 モノが語る鉄道史
第6章 よみがえる新橋停車場
著者等紹介
斉藤進[サイトウススム]
1957年、東京都台東区生まれ。立命館大学文学部史学科卒業。公益財団法人東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター職員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
2
f005、もともと日本初の鉄道路線である「新橋~横浜」という区間はどっちの駅も位置を移動しているんですが、その後、汐留駅という貨物駅になったのちに遺構として発掘されていた、というのはつい最近まで知らなかったなぁ。それなりに記録も残っているものの、そもそも図面にはない上下水道とか遺構の実際の位置とか、当時の生活の様子などはまあ掘り出してみないとわからないよね、というのはもっともですよね。当時のトイレが破棄される時点で切符などがそこに捨てられたようなんですが、この機微がちょっとわからなくて不思議、なんでだろ。2015/01/20
えひめみかん
0
鉄道の歴史全般に触れていて、短いながらも濃い内容になっている2023/11/19
-
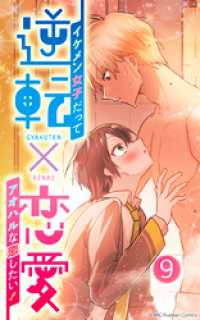
- 電子書籍
- 逆転×恋愛~イケメン女子だってアオハル…