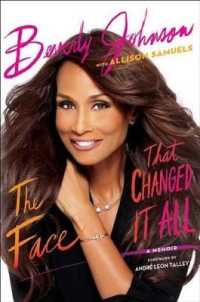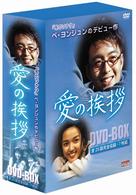内容説明
ビーレフェルト大学において1992/93年冬学期に開講された「社会」とは何かを徹底的に問うた入門講義(全13回)の全訳。ルーマンの問題意識、それへの取り組み、さらにその取り組みを積み重ねていく過程が、つぎからつぎへと語られていく。
目次
1 社会システムとしての社会
2 コミュニケーション・メディア
3 進化
4 分化
5 自己記述
著者等紹介
ルーマン,ニクラス[ルーマン,ニクラス][Luhmann,Niklas]
1927‐1998年。20世紀を代表する社会学者の一人。もっとも重要な功績は、新たなシステム理論を社会学理論に結びつけ、一つの社会理論を発展させたことにある。フライブルク大学で法律を学んだ後、ニーダーザクセン州の行政官として勤務。タルコット・パーソンズの社会学に徹底的に取り組むためハーバード大学へ留学。その後、ミュンスター大学で博士号、教授資格を1年で取得。1969年、新設されたビーレフェルト大学に教授として就任。1993年に定年退官
ベッカー,ディルク[ベッカー,ディルク][Baecker,Dirk]
ツェッペリン大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
機能システムと差異の理論を軸に、社会を一つの全体社会として設定し、従来の社会は閉鎖系システムの分出の仕方によって階層化や分化といったバージョンと著者は捉える。1990年代の13回の講義を収めた本書は、差異によってコミュニケーションを行う機能システムの変容を、対称的な口語コミュニケーションから非対称的な文字コミュニケーションへと転換するメディアから説明する一方、危機回避のために複雑性を縮減した効果としての意味をシステムが蓄積し、その閉鎖性(包摂/排除)を強化する様を、進化、分化、自己記述の概念から概説する。2024/08/08
1
再読。面白すぎる。ていうか、下手な解説よりも分かりやすい。例えば、言語の問題を考えてみたとき、そこにメディア/形式という枠組みを持ち出し、文字/印刷技術の「形式」が如何に口頭コミュニケーションの対称性を、書記コミュニケーションの非対称性という「メディア」として繰り込まれてゆくのか、マクルーハンにも繋げられる話。或いは、近代における複雑性の縮減としての機能分化が不可避的に包摂/排除を導くこと、ただ同時にその排除がネガティブな形での包摂(宗教的原理主義など)してしまうことなんか、アクチュアル。2023/11/26