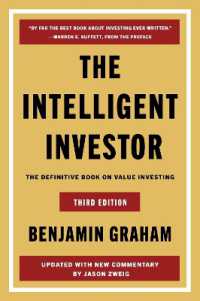出版社内容情報
「ぼくらの非モテ研究会」は男性の生きづらさを語り合う場としての当事者研究グループである。非モテ研では、幅広い分野で注目されている当事者研究の手法を応用し、これまであまり語られてこなかった男性たちの「痛み・悲しみ」だけでなく、「非モテ」の現状を打開しようとする、切実さのなかにもユーモアあふれる研究成果を蓄積している。
「女神」「ポジティブ妄想」「自爆型告白」などの観点からは、単純な「非モテ=恋人がいない」という考え方では捉えきれない、親からの影響、学生時代の経験、社会からの疎外感・孤独感など、多様な物語が浮かび上がる。
研究会を主宰する男性学研究者を中心に、ジェンダーやフェミニズムの概況を踏まえながら、「非モテ」をキーワードに立ち上がる男性たちの語りに寄り添い、ともに研究してきた成果をまとめる。
非モテ研メンバーたちの当事者研究も豊富に盛り込み、既存の男性学では「語れない/語らない」とされている男性たちの切実な語りから多様でよりよい生き方を探る、新しい時代の男性学を切り開く一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スシローよりはま寿司が好きな寺
71
「モテないけど生きてます?私の事じゃないか!」と勇んで読む。昔からモテなかったが、年々ますますモテなくなるので時々ワケもなく笑うほどである。はは。しかも歳を取るとモテなさを増しながら性欲が衰えてゆくのだから、人生とはよく出来ている。モテないのも今やソーシャルディスタンスのうちである。不本意だが。しかしまだまだ男社会の世の中でも、男として弱者・劣等者のコンプレックスを抱いて苦しんでいる者はいつの世も一定で存在する。そういう人達による当事者研究の成果が集まった一冊。頷きながら読んだ。真面目な本である。お薦め。2021/01/21
shikashika555
58
男性の非モテ問題は社会性の問題なのだ。 そしてそれは男性だけの問題ではなく女性も含めた全ての人にとって問題になりうる。 文中で語られる彼らの被害体験は そのまま女性が受けている性差別に由来する(と思っていた)被害とほとんどが同じものであることに驚いた。 被害女性からはもしかしたら「見えない存在」であるかもしれない彼らの体験を知ることで、新しく差別の構造が見えてきて 打開策も開けるかもしれない。 一人の人間が100%加害者や被害者であるはずは無い。 1人の中に加害性と被害性があるのだ。 おすすめ本。2021/06/14
ホークス
39
2020年刊。題名と違ってかなり重く、赤裸々な内容。コンプレックスに向き合うのは辛い。「勝て」「支配せよ」という男社会の教義に背くのも恐怖だ。どちらも他人に言えないから余計に苦しい。見えない出口を探すヤケクソの勇気を感じた。もっと重要なのは、一人一人違う困難を抱えた自称「非モテ」たちが、それぞれの挑戦を共有し支えあう活動をしている事だ。テーマも方法も違い、理解できない場合さえあるのに、互いの苦しさと希望は感じ合える。もしかしたら、人間全体の行き詰まりへのヒントが隠れてるかも、などと夢想してしまった。2023/10/23
akihiko810/アカウント移行中
32
非モテについての当事者研究。印象度B 通っているNPOでの今月の課題図書だったらしく、借りて読んだ。 感想は、本人たちは至って真面目に悩んでいるのだろうけど、モテ/非モテにこだわりすぎていることに一抹のキモさがにじみ出ていると思った。申し訳ないけど。なんというか、そこに自意識が見え隠れしているので、キモさが露呈していると思った。私もモテない人間なのでそれに悩んだりするけど、趣味もったり色々忙しくしているので致命的に悩まずに済んでいる。非モテに大いに悩む人は、趣味持ったりして人生の使い方を(続く 2021/02/13
のんぴ
29
社会的にも意義のあるアカデミックな研究だと思う。自分を持て余し、自暴自棄になって、アホなことをやらかす前に、勇気を出して、非モテ研につながり、そのモヤモヤの根源を深堀りして、名前を付けて、コントロール可能な大きさにして、モテないままでも生きていってほしい。2023/11/21
-
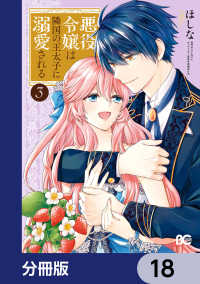
- 電子書籍
- 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される【分…