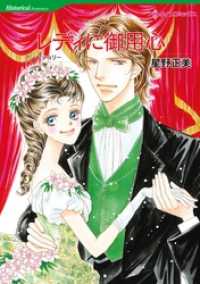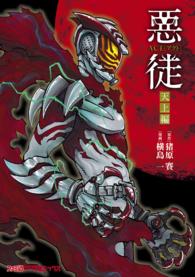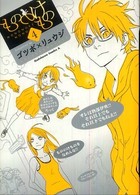内容説明
断髪、自転車、海老茶袴、ラブ…。学校という近代化装置に組み込まれた少女たち=女学生は、明治という時代のなかで何者として存在し、社会はどのようなまなざしを向けたのか。装いや小説・少女雑誌での表象などを手がかりに、女学生の誕生とその系譜をたどる。
目次
第1章 「女学生」の誕生
第2章 髷からの解放
第3章 風のいたずら
第4章 宙に揺れることば
第5章 恋と脳病
第6章 「少女」への凝集化
第7章 『森』―近代型女人の神話と時代
第8章 フェミニティーの世紀末
著者等紹介
本田和子[ホンダマスコ]
1931年、新潟県生まれ。お茶の水女子大学卒業。お茶の水女子大学学長を経て、お茶の水女子大学名誉教授。専攻は児童文化論、児童社会史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
1
k006、大雑把に言うと女が男と対等に口をきくこと、そして躍りを踊るということは「商売女」しか知らなかったため、西洋化を計ろうとした女学生たちの振る舞いはどうしても商売女としか認識出来なかったという辺りも凄まじいものの、その差別意識に乗っかりただ預かっているだけの良家の子女を勝手に男に売り渡す下宿のおかみもさすがになぁ…。全体的にこの本でも言われていたように「男が罪を犯し、女がその責任を負う」スタイルなんだよな、欲情しながら見下すってのもわかりやすいかな…。通俗小説の顛末をその意識と連動するのも面白いね。2020/01/24
姫宮紅真
1
面白かった。初めは叙情的な文体に少し戸惑ったものの、少女文化をその内側から位置づけ解き明かそうとする試みなのだと解題を読んで理解した。明治の女学生に向けられた視線、彼女たち自身が求め作り出した世界、時に軽視される少女文化というものに現代のオタク黒歴史に通じるものを感じたりして。2016/01/19
8
0
創世記の“女学生”とはナニモノだったのかを問うた本。著者は最後をボヤかしたが、実はそれほど明るい存在では無かった様に思えた。まあ、その後社会全体が悪い方に流れていくので、仕方が無い面もあるのだけど。最後、野上弥生子が俎上に上げられたけど、女子の進学率も上っていた都心の女学生像はまた違ったのではないかと思う。“女子教育”と向き合う上で、意識すべき事は見えてきた気がする。 とりあえず未読の野上弥生子『森』を読まなくては。2024/03/17
Rick‘s cafe
0
近代化と女子教育の象徴で、海老茶袴を履き、自転車で風を切り、恋に恋する乙女としてロマンチックに描かれがちな「女学生」たち。現代においては「はいからさん」と呼ぶ方がイメージしやすいだろうか。風俗画や少女雑誌、小説などから、服装や言語を読み解き、明治国家において背負わされた役割とその制度から離れて連帯し、幻想の共同体を作り上げる過程を丁寧に追っている。軽い侮蔑の対象であると同時に、憧れの存在でもあるそんな毀誉褒貶の二重写しの存在を紐解けば、社会から宙吊りにされた「少女」たちの姿が見えてくる。2022/08/27
ガジ
0
修論に使うもの、再読キャンペーン。 少女論といえば本田和子だと思っている。再読すると4章6章が接続できるな、とか7章おもろいな、とかなる。今田さんの解題もよい。本田学の魅力は、その当事者性なのだろうか。、2022/01/17