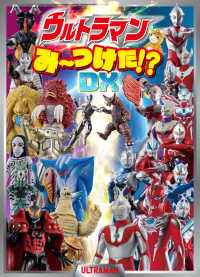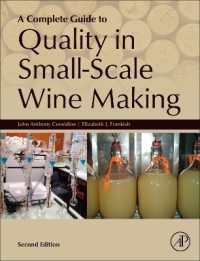出版社内容情報
《内容》 痴呆を疑った場合の具体的な診察法、主治医意見書記入上の留意点、患者・介護者への対応、人権擁護に関する知識など、かかりつけ医にとって必要な事項をすべて把握できる内容。 《目次》 第1章 地域医療における痴呆診療でかかりつけ医に求められること 1.はじめに 2.かかりつけ医への期待 3.地域医療とかかりつけ医 4.地域ケアシステム 5.痴呆性高齢者のケア 6.かかりつけ医が痴呆性高齢者を診察する際に望まれる対応 7.「介護保険主治医資料」と「居宅療養管理指導内容」の利用 第2章 痴呆の症状と特徴 1.痴呆とは何か 2.痴呆の症状 第3章 痴呆の精神症状と行動の障害とその診かた 1.痴呆の精神症状・行動の障害の臨床的意義 2.老年期の痴呆にみられる主な精神症状と行動の障害 3.精神症状と行動の障害の頻度に影響する要因 4.薬物療法の考え方 第4章 痴呆の原因と間違えられやすい状態 1.痴呆の原因疾患 2.痴呆と間違えられやすい状態 第5章 痴呆をどのように疑うか 1.受診の契機 2.痴呆のアセスメント 3.改訂長谷川式簡易知能評価スケール 4.N式老年者用精神状態評価尺度(NMスケール) 5.Functional Assessment Staging(FAST) 第6章 痴呆の診察の実際 1.一般的な事柄 2.診察の実際 第7章 介護保険の主治医意見書では何が求められるか 1.在宅痴呆性高齢者の介護の実態 2.痴呆性高齢者の介護者にはどのような負担があるのか 3.意見書記載上の留意点 4.ケアプランを作成・実施上の留意点 第8章 痴呆の在宅ケアでかかりつけ医が注意すべきこと 1.最初のコンタクトから診断へ 2.早期診断の意義 3.専門医への紹介 4.介護指導の原則 5.在宅介護をする場合 6.治療におけるかかりつけ医の役割,専門医の役割 7.介護者の指導 8.日常行動の介護 9.痴呆症を原因とする行動の障害や精神症状に対する介護 第9章 治療における人権擁護 1.診察の開始 2.診断の結果を誰に伝えるか 3.インフォームドコンセント 4.チームアプローチと医療情報の提供 第10章 人権擁護に関する知識(1)―介護保険下の福祉サービス 1.介護保険と措置制度 2.地域福祉権利擁護事業 第11章 人権擁護に関する知識(2)―成年後見制度 1.後見類型 2.保佐類型 3.補助類型(新設) 4.任意後見制度(新設) 第12章 人権擁護に関する知識(3)―法律行為と意思能力 1.一般的注意点 2.民事鑑定の判断基準
内容説明
痴呆の診断は検査による数値で示されるものではないため、難しいといわれる。しかし、家族から本人の日常生活の様子を聞くことができれば決して難しくはない。本書ではそのための具体的な手順を示した。
目次
地域医療における痴呆診療でかかりつけ医に求められること
痴呆の症状と特徴
痴呆の精神症状と行動の障害とその診かた
痴呆の原因と間違えられやすい状態
痴呆をどのように疑うか
痴呆の診察の実際
介護保険の主治医意見書では何が求められるか
痴呆の在宅ケアでかかりつけ医が注意すべきこと
治療における人権擁護
人権擁護に関する知識(介護保険下の福祉サービス;成年後見制度;法律行為と意思能力)