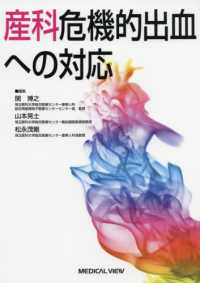- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
3.11から10年。「被災地」という渇いた語感とはかけ離れた、生活の営みが浮き彫りとなる。10年のフィールドワークから、民俗学者として問いかける。みなさんの生きる土地には、復興の繰り返しの歴史があり、それぞれの時代を全力で生きた人々がいた。一人ひとりは家族や隣人の歴史として刻み込まれ、過去と現在をつないでいる。震災10年という時間から、未来を展望するとき、そこにどんな暮らしをイメージしますか?
目次
第1章 遥かなる鮎川
第2章 捕鯨の鮎川か、鮎川の捕鯨か
第3章 クジラの臭いは繁栄の匂い
第4章 失敗しても磯からやり直せばいい
第5章 突拍子もないほどの賑わい
第6章 復興10年と地域文化のこれから
著者等紹介
加藤幸治[カトウコウジ]
武蔵野美術大学教養文化・学芸員課程教授。専門は民俗学、博物館学。静岡県出身。総合研究大学院大学文化科学研究科比較文化学専攻修了、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
さんつきくん
4
宮城県の牡鹿半島・鮎川と言う地域をテーマに民族学者である著者が書いた一冊。鮎川と言えば鯨である。そして金華山航路の玄関口。もともと小さな集落だったが、明治時代に企業誘致し、それまで個人で捕っていたのが、ノルウェー式の技術を受け入れて集団捕るようになった。1950年代に絶頂期をむかえ、商業捕鯨禁止になるまで栄えた捕鯨。そして東日本大震災。地域の古い道具を再生するプロジェクトを著者と大学のゼミ生が行う。一番は栄えた時の鯨まつりの写真が印象に残った。今度、鮎川に行こうと思う。2021/09/16
Go Extreme
3
遥かなる鮎川:牡鹿半島・鮎川へのいざない 港の風景・鮎川の町並み 黄金時代の風景 捕鯨の鮎川か、鮎川の捕鯨か:寄り鯨の伝統と仙台藩の捕鯨 近代捕鯨の導入と鮎川の捕鯨前史 大企業の前線基地建設と捕鯨産業 地元資本の家業としての捕鯨 クジラの臭いは繁栄の匂い:黄金時代の到来と南氷洋捕鯨 調査捕鯨の時代と小型沿岸捕鯨へ―商業捕鯨モラトリアム以降 航海の記憶クジラトレジャーと鯨歯工芸品 クジラのミュージアムと地域文化 失敗しても磯からやり直せばいい 突拍子もないほどの賑わい 復興10年と地域文化のこれから2021/05/13
りょうた
1
くじらのまち鮎川のダイナミックな文化史。震災から立ち上がる中で海水温が上昇し、三陸の漁村は生業の変化を求められていて、長年続いてきた文化を保つことが難しくなってきている中、このように記録することは非常に重要な仕事だと感じました。2025/04/01