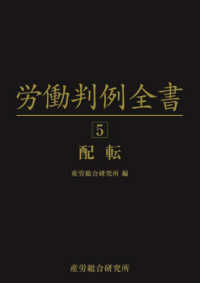出版社内容情報
下水道の整備が進むとともに、下水汚泥をどう処理するかはコストもかかることからどこの自治体でも大きな負担となっている。埋め立て、焼却、バイオマス利用、マテリアル利用などへの試みがある一方、その減量化は、まず大切な要件である。本書は、この下水汚泥に多く含まれるタンパク質を分解するB.subtilis IRIN-6株(プロテアーゼ<タンパク質分解酵素>生産菌)を用いた下水汚泥の減量化の実験と考察をまとめたものである。特に本菌は、筋肉性タンパク質より分解しにくいと考えられている心臓の筋肉(心筋)の分解性も高い。
下水汚泥の減量化に取り組まれている関係者の方には、ぜひご一読願えればと願っている。
また、同書内容を英文でも載せているので、日本以外でも利用されることを願っている。
1. 実験方法
1-1. 施設の概要と汚泥減量化データの取得方法
1-2 種菌の詳細と添加方法
1-3 cooked meat medium 懸濁物(CMM-SS)の除去率(心筋分解活性)の測定
1-4 希釈法による活性汚泥中の微生物の分析
1-5 微生物の同定
1-6 汚泥貯留槽からの酵母類(LL1-1、L1-2及びM1-1)の単離
1-7 位相差顕微鏡を用いたフロックの観察
1-8 腐植酸(アルカリ可溶性物質)の抽出
1-9 活性汚泥微生物の生育阻害に関する評価
2. 実験結果および考察
2-1 種菌の生育
2-2 種菌添加後の搬出汚泥量の減量化
2-3 種菌のcooked meat medium懸濁物質(CMM-SS)除去率(心筋分解活性)
2-4 種菌の運命:IRIN-6株の生存とIRIN-6株のCMM-SS除去率の変化
2-5 フロック観察の結果
2-6 アルカリ可溶性物質の抽出
2-7 酵母類とカビ類の出現
2-8 IRN-xxx-H株の酵母類やカビとの共存によるタンパク質分解活性の増進
2-9 B.subtilis以外で高頻度で検出された細菌類とそれらの基質分解性
3. 汚泥分解過程に関する考察と汚泥安定化に関する考察およびまとめ
3-1 フロック分解過程、フロックの構造および安定化
3-2 IRIN-6株の生存とIRIN-6 株のタンパク分解性の変化
3-3 IRN-xxx-H株の生育阻害と対策
3-4 下水処理における反応式
入江鐐三[イリエ リョウゾウ]
著・文・その他
目次
1 実験方法(施設の概要と汚泥減量化データの取得方法;種菌の詳細と添加方法;cooked meat medium懸濁物(CMM‐SS)の除去率(心筋分解活性)の測定 ほか)
2 実験結果および考察(種菌の生育;種菌添加後の搬出汚泥量の減量化;種菌のcooked meat medium懸濁物質(CMM‐SS)除去率(心筋分解活性) ほか)
汚泥分解過程に関する考察と汚泥安定化に関する考察およびまとめ(フロック分解過程、フロックの構造および安定化;IRIN‐6株の生存とIRIN‐6株のタンパク分解性の変化;IRN‐xxx‐H株の生育阻害と対策 ほか)
著者等紹介
入江鐐三[イリエリョウゾウ]
農学博士。1938年香川県に生まれる。1961年京都大学農学部農芸化学科卒業。1963年同農学研究科修士課程修了。三重大学助手(農学部農芸化学科)。1970年信州大学助教授(農学部農芸化学科)。1987年信州大学教授(農学部生物資源学科)。2004年同定年退職。名誉教授。同年七宝バイオ資材研究所設立。2018年受勲(瑞宝中綬章)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 白くぬれた庭に充てる手紙
-

- 電子書籍
- 蛇神カグラ! 分冊版 5 webアクシ…