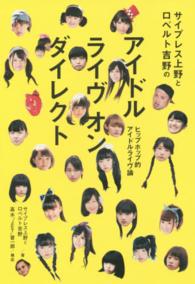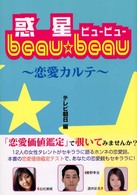内容説明
いつ聞いても、何度聞いても、やっぱり同じところで笑ってしまう。話芸には、はなし家の修練と歴史がある。
目次
江戸編(江戸落語の始まり;日本橋にいた江戸落語の祖 ほか)
明治/大正編(明治維新と爆弾可楽;圓朝(その1 抜群の創作力) ほか)
戦前編(昭和初期の落語界事情;愛国演芸同盟の結成 ほか)
戦後編(平和の訪れと寄席復興;第三次、四次落語研究会 ほか)
現代編(寄席の受難期;「民族芸能を守る会」結成 ほか)
著者等紹介
柏木新[カシワギシン]
1948年生まれ。話芸史研究家・演芸評論家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
greenish 🌿
50
「東京民報」’08年~’11年の連載を書籍化した一冊。江戸落語の始まりから現代落語の幕開けまで、江戸・東京の落語界の歴史を紐解く ---江戸編/明治・大正編/戦前編/戦後編/現代編(上)/現代編(下)の6章の構成。戦国時代の御伽衆を源流とした江戸落語の祖、落語中興の祖・圓朝の話芸、戦争に翻弄された禁演落語と国策落語、戦後の黄金時代(文楽・志ん生・圓生・正蔵・小さん)、落語協会分裂騒動、などが興味深かった。 江戸の時代から権力・闘争に翻弄された落語。平和だからこその”笑いの文化”…未来永劫発展して欲しい。2017/07/10
6だ
2
週刊新聞「東京民放」に2011年まで連載されていた記事を纏めた一冊。通人には知った話も多かろうが、最新の研究成果(武左衛門流罪への疑義)や連載読者からのタレコミ(文楽最後の高座)も盛り込まれ一読の価値は十分にある。その他にも、落語の歴史とも言える出来事を、戦国時代の御伽衆御咄衆の存在から七代目圓生襲名騒動まで、ほぼ余すところなく網羅しているため、最近落語に興味を持った人やより詳しく知りたいという人への落語史入門書としても推奨できる内容。これより詳しく知りたい人は専門書に手を出すか寄席に行くしかないだろう。2012/06/03
栗山いなり
1
落語が辿ってきた歴史を知ることができたのと同時に文化や芸術に関わる人達の多くがなぜ平和を願い反戦を謳うのか分かった…気がした2019/04/20
masasamm
0
落語の歴史の概観。読みやすい。2023/03/21
prefabjubilo
0
ざーっと落語の歴史!あまりに誤植が多いのはなぜ?2020/09/10