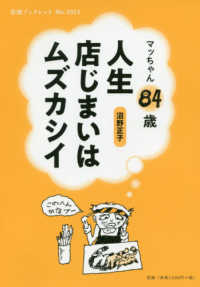出版社内容情報
「私は、カナダ文学を
ポストコロニアルの文学という大きな視野から
論じる必要があることを、痛感している。」
博覧強記にして研究の道半ばにして早世した、
希代のカナダ文学研究者の
生前に発表した学術論文、評論、書評、新聞寄稿コラム
から厳選した著作集成。
研究の中心にあったマイケル・オンダーチェ論を始め、
多文化主義国家カナダのマイノリティ作家を、
社会・文化的背景を含めて論じていく著作群は、
日本におけるカナダ文学観を大いに塗り替える。
[本書の特徴]
第一部にカナダ文学通史と背景を扱う著作をまとめ、
大学一般教養のカナダ文学入門講座の教科書に
適したものとなっています。
第二部はマイケル・オンダーチェの作品論で構成。
日本でも人気のある『イギリス人の患者』の作者の世界を、
カナダ文学という枠組みから考察し、
広く文学愛好者に刺激的な読みが展開されます。
第三部では著者の専門である、20世紀末から21世紀初頭の、
カナダのマイノリティ作家論が並び、
和訳が刊行されていない重要作家の読書案内として、
またポストコロニアリズムと多文化主義の接点を
示唆する論として、
学部生の卒論指導ないし大学院博士前期・修士課程の
教材にもたえる重厚な内容です。
序文に代えて
マイノリティ文学からポストコロニアル文学へ
第一部 21 世紀に向かうカナダ文学史
英系カナダの文学
作品紹介
キャロル・シールズ
ティモシー・フィンドリー
ヤン・マーテル
キャサリン・ゴヴィエ
マーガレット・アトウッド
アリステア・マクラウド
アリス・マンロー
ウィリアム・ギブスン 他
多文化と多文化主義のはざま:カナダ文学再考
過去へ、現在へ:新世紀カナダと文化の力
第二部 マイケル・オンダーチェ
オンダーチェの『ビリー・ザ・キッド作品集』
「父」なる故郷:
Running in the Family(『家族を駆け抜けて』)
に見る自伝性の破綻
English Patient( 『イギリス人の患者』)を
「読む」
オンダーチェの遠近法
── Anil’s Ghost を契機として
第三部 多文化主義国家の英語文学
ある起源の物語
──トマス・キングの「インディアン」と
コロンブス神話
寄宿学校の爪痕
──カナダの先住民作家と英語の関係
作品紹介
ローレンス・ヒル
ポーリーン・ジョンスン
ビアトリス・カルトン・モニジェー
カレン・レヴァイン
ロイ・キヨオカ
ジョイ・コガワ
ケリ・サカモト
ディオンヌ・ブランド
シャイアム・セルヴァデュレイ 他
『美しき敗者たち』
──レナード・コーエンの華麗なる孤独
アニタ・ラウ・バダミのインド、あるいはカナダ
ハイフンからの眺め
──フレッド・ワーとカナダ文学の文脈
講演
ホーム・アンド・アウェイ
移民作家の故郷とは
付録
英語論文 The Structure of Joy Kogawa’s Obasan
藤本 陽子[フジモト ヨウコ]
Yoko Fujimoto
ふじもとようこ
元早稲田大学文学学術院教授。
東京外国語大学卒。
早稲田大学文学研究科博士課程単位取得退学。
在学中にトロント大学に留学し、修士号取得。
専修大学文学部助教授、
早稲田大学第一・第二文学部助教授を経て
同教授となる。
1990年代から日本語と英語の両方で精力的に研究、
執筆活動を行い、21 世紀に入ってから
ロンドン大学客員研究員、国際学会でも多数発表。
研究対象はカナダ文学に限らず米文学や、
水村美苗にも及ぶ。
2011年に病で急逝するまで、10年あまりにわたり
「北海道新聞」で連載を担当し、
広くカナダ文学・文化の普及にも務めた。
著訳書に『現代カナダを知るための57章
エリア・スタディーズ』(執筆、
飯野正子・竹中豊 編著、明石書店、2010年)、
『はじめて出会うカナダ
日加修好80周年,カナダと日本を知るために』
(分担執筆「4 カナダの文学」日本カナ…
堤 稔子[ツツミ トシコ]
桜美林大学名誉教授。
日本カナダ文学会顧問・元会長。
東京女子大学、米国ワシントン大学卒(Ph.D.)。
著書:
『カナダの文学と社会』(こびあん書房、1995年)、
『日本とカナダの比較文学的研究』
(共著、文芸広場社、1985年)ほか。
中山 多恵子[ナカヤマ タエコ]
元在日カナダ大使館広報部。
出版・映像担当として、カナダ文化の紹介と
理解促進、日加交流に努める。
馬場 広信[ババ ヒロノブ]
早稲田大学、青山学院大学ほか非常勤講師。
比較文化(文学・動画)、博士(文学)。
早稲田大学文学研究科にて、藤本陽子指導の下、
博士論文「アトム・エゴヤン作品に見る
カナダのアルメニア人表象:
映画『アララトの聖母』を中心に」を執筆。
内容説明
早逝の気鋭の研究者が移民国家カナダの生々しい鼓動を伝える斬新な文学論!オンダーチェを中心とするカナダの“マイノリティ”や先住民作家の論考、マンロー、シールズ、アトウッドらの作品に関する多角的なエッセイの集成。
目次
序文に代えて―マイノリティ文学からポストコロニアル文学へ
第1部 21世紀に向かうカナダ文学史(英系カナダの文学;PC“ポリティカル・コレクトネス”に関する覚書―カナダ文学の周辺から;移民=マイノリティから普遍へ ほか)
第2部 マイケル・オンダーチェ(書評『ビリー・ザ・キッド全仕事』―怖くて愉快なグロテスク;オンダーチェの『ビリー・ザ・キッド作品集』―旅する伝説から時代の表舞台へ;『家族を駆け抜けて』訳者あとがき ほか)
第3部 多文化主義国家の英語文学(ローレンス・ヒル『ザ・ブック・オヴ・ニグロズ』;E.ポーリーン・ジョンスン「私の櫂がかなでる歌」、マーガレット・アトウッド『ポーリーン』;ハーパー連邦首相の先住民寄宿学校問題公式謝罪 ほか)
付録 英語論文The Structure of Joy Kogawa’s Obasan
著者等紹介
藤本陽子[フジモトヨウコ]
1958~2011。元早稲田大学文学研究科教授。東京外国語大学卒。トロント大学大学院(M.A.)。早稲田大学文学研究科博士課程満期退学。専修大学文学部助教授、早稲田大学文学研究科助教授を経て同教授となる。日本語と英語の両方で精力的に研究、執筆活動を行い、国際学会でも多数発表。21世紀に入ってからロンドン大学客員研究員。2011年に病で急逝するまで、10年あまりにわたり「北海道新聞」で連載を担当し、日本でカナダ文学・文化の紹介にも努めた
堤稔子[ツツミトシコ]
桜美林大学名誉教授。日本カナダ文学会顧問・元会長。東京女子大学・米国ワシントン大学卒(Ph.D.)
中山多恵子[ナカヤマタエコ]
元在日カナダ大使館広報部。出版・映像担当として、カナダ文化の紹介と理解促進、日加交流に努める
馬場広信[ババヒロノブ]
早稲田大学、青山学院大学ほか非常勤講師。比較文化(文学・動画)、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- Best Loser Wins ――人…