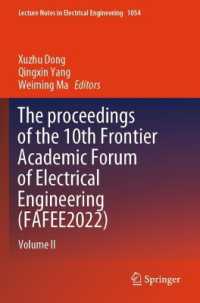内容説明
栄養素としておなじみのタンパク質。でも、体の材料のみならず、心や意識の働きにも深く関わった、生命活動に欠かせない物質であることはあまり知られていない。創薬の基礎になる「酵素」や「受容体」の働き、病気との関わりなども含め、タンパク質の全体像を概観する。
目次
第1章 アミノ酸の最新研究から見えてきたこと
第2章 タンパク質と消化・味覚との関わり
第3章 酵素・受容体・コラーゲン~タンパク質の多様な働き
第4章 生命活動とタンパク質のつながり
第5章 タンパク質の変異が病気を引き起こす!
第6章 謎のタンパク質・プリオン―「狂牛病」をめぐるミステリー
第7章 心の病気・クスリ・タンパク質のつながり
著者等紹介
石浦章一[イシウラショウイチ]
1950年、石川県生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業、同理学系大学院修了。国立精神・神経センター神経研究所、東京大学分子細胞生物学研究所を経て、東京大学大学院総合文化研究科教授。理学博士。専門は、ヒトの認知機能を分子レベルで研究する分子認知科学、ほかにタンパク質生化学、分子生物学など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
27
タイトルのとおり、タンパク質はすごい! 食べ物の美味しさの要因はタンパク質にあるし、身体をつくるのはタンパク質、アルツハイマー病などの病気の原因もタンパク質で説明できる。さらに薬の効果、なぜ個人差があるか個人でも薬によっては効きにくいものがあるというのも説明できる。わずか20種類の働きで人間も含めたさまざまな生物のいろいろな活動を支える。奥が深いのは同じ種類も生物でも同じ効果になるわけではないというところだろうか。もっと勉強していきたい。2025/09/22
Sato
10
糖質制限ダイエットなどで、何かと最近チヤホヤされているタンパク質。本のタイトル通り、タンパク質は思っていた以上にすごかった。人体を作っているのはタンパク質というのは以前から理解しているつもりだったが、ガン、遺伝病や難病、精神疾患など様々な病気もタンパク質が正常に働かなくなったことで起こるらしい。そして何かを食べて「美味しい」と感じる旨味や甘味、苦味など味をキャッチする「受容体」もタンパク質。タンパク質はすべての生命現象に関わっていた。所々難しい記述もあるが、文系でも読めるライトサイエンス本。2019/01/15
手押し戦車
9
タンパク質は窒素が多く飢餓の状態で過剰に摂ると代謝の時にアンモニアが多く出て痛風などになる。バリン、ロイシン、イソロイシンのアミノ酸は筋肉を構成するタンパク質でグルタミンは筋分解を防いだり味覚を支配するグルタミン酸が有る。タンパク質は生命を維持するのに遺伝子からプログラムされたアミノ酸を合成し体と言う形を作っている。コーヒのカフェインは脳のアデノシン受容体が興奮、覚醒を抑えるのを阻害しカフェインが受容体と結合し眠気をさます。病気や型ちを創造する芸術家のお手伝い役だが実は無理をさせると病気を引きおこさす2014/10/22
ゆかたん
8
タンパク質がすごい事は分かった。 病気の原因もタンパク質っていうことには驚いた。ただ、化学式は難しくてわからなかった。2019/11/08
とく だま
5
食物をアミノ酸に分解して繋ぎ直してタンパク質を組み立て身体へ作用する。DNAの仕業かと思いきやたんぱく質も含め作用しきりのようだわ。作用するストーリーは解らない部分も多く残っているようで、BSEや薬の話も興味深く面白かった。2024/07/25
-

- 電子書籍
- 刑事司法記録の保存と閲覧---記録公開…