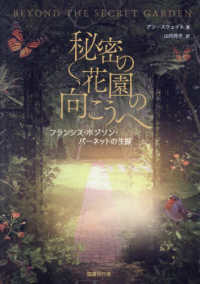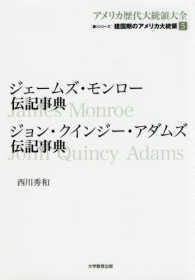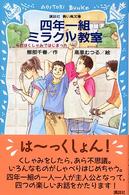内容説明
医療従事者の教育・研究のために、解剖体として遺体を捧げる「献体」。この献体を希望する人が増加し、密かに世間の注目を集めている。どうすれば身体を提供できるようになるのか?遺体はどのように解剖され、最後はどうなるのだろうか?デリケートなテーマだけに、語られることが少なかった献体。本書は、その現状を真正面から伝える初めての書籍である。
目次
第1章 献体をすること
第2章 献体者を見送る側―遺族の立場
第3章 献体者を受け入れる側―大学側の実務
第4章 遺体の扱い―解剖実習と学生
第5章 献体運動はどのように行われているのか
第6章 世界と日本の献体事情
第7章 日本における人体解剖と献体の歴史
第8章 世界における人体解剖の歴史
著者等紹介
坂井建雄[サカイタツオ]
順天堂大学医学部教授(解剖学・生体構造科学)。1953年大阪府生まれ。1978年東京大学医学部医学科卒業。ハイデルベルク大学研究員、東京大学医学部解剖学助教授を経て、1990年から現職。主な研究・活動領域は、解剖学、腎臓と血管系の細胞生物学、献体と解剖学の普及、医学と解剖学の歴史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Tui
28
父が献体すると言っている。はあいいんでないのといった感じだが、とりあえず何も知らないでいるのもよくないなと思い、図書館で借りてみた。日本は献体が盛んで、医大によっては受け入れを制限しているところもあるとか。没後、家族の元に遺骨が戻るまで2,3年要するとか(遺体処理に時間がかかるのです)。解剖実習中の学生に対し、献体登録している方の総会に参加する機会を医大が設けているとか(素晴らしい!)。読み終えて、賛成の気持ちに変わりはないけど、父がどこまで知った上での考えなのか、いちおう聞いておこうかなと思った。2018/11/15
パズル
11
医学生にとっての献体が、知識や技術の為だけでない事がとても丁寧に書かれていました。 目の前の遺体を、人生を全うした一人の人間としてとらえ、敬意を払う事は私にとっても自然な事です。ですから、アメリカの献体についてのくだりは驚きました。2014/11/13
和草(にこぐさ)
10
献体する人が増えている。死後の選択が自分でできることも一因である様に思う。自分の死後を自分自身で決めるのは当たり前と思っていたが、一昔前では「お墓」に入るのが当たり前であった。解剖学の歴史もあり、自分自身の最後の選択をよく考えたいと思う。2014/01/19
Humbaba
7
死生観の変化のためか,献体に応じる人の数は増えている.しかし,だからこそ医学を志す人は感謝の心を失ってはいけないだろう.トラブルを回避するために,本人だけでなく家族の同意もとるというのは,手間はかかるが避けるべきではないことでもある.2013/02/25
なめこ
3
死後なんらかの役に立ちたいと思い、前から興味はあった。実際の現場を垣間見ることができて、あらためて献体したいと思ったし、同時に難しさも痛感。私は、有益なことならいくらでも使って!と思うが、体を切り刻むという意味で拒否反応示す人もいるわけだ。生前に家族の同意を得る、って一番むずかしくて一番重要。本書はそのあたり、是非にぜひにと勧めるわけでもなく公平なのがよいが、ちょっと自分の大学を持ち上げすぎに感じたな。それを差し引いても貴重な書。2016/04/02