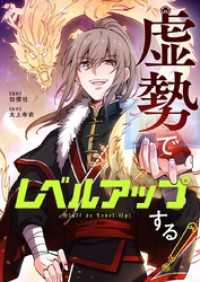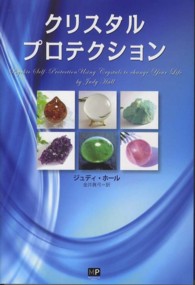内容説明
心の病については数々の情報が公開され始めた。そして、周囲の理解や対応が深まる一方で、歪みも生じている。際限ない「自称患者」にどう対応するべきか?治療や司法のための「レッテル貼り」は排除や差別にならないか?社会に蔓延(バブル化)する心の病をとりまく現象に、精神科医が一石を投じる。
目次
第1章 うつ病(光の中に出たうつ病;うつ病とは何か ほか)
第2章 アスペルガー障害(光の中に出てきたもうひとつの病;発達障害とは何か ほか)
第3章 アルコール依存症(酔っ払い天国の崩壊;アルコール依存症とは何か ほか)
第4章 PTSD(バブルへのブレーキがない病;PTSDとは何か ほか)
第5章 サイコバブルとサイコバブル(それは、BUBBLE;いま、アブノーマライゼーション ほか)
著者等紹介
林公一[ハヤシキミカズ]
精神科医。医学博士。月のアクセス数がゆうに150万を超える「Dr林のこころと脳の相談室」を1997年から運営中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
3
本来なら病気ではないものが病気と診断されてしまったがための悲劇が多い、というのはしごく納得ですが、やはり何をして「病気」と認められるのかどうかがイマイチフルイチわからない。正味の病であるなら早めの治療・投薬が有効である、と非常に強く訴えられているので尚更のこと。2014/08/24
Sunekosuring
3
タイトル通り、心の病と社会との関係を書いた本。心の病が社会的に受け入れられるようになったことは良いことだが、それゆえ「病気」を増やしてしまう、また医者の救いたいという気持ちが病とは言いがたいものを病にしてしまう、しかしそれを強調しすぎると救えたはずの人が救えなくなるという結論の難しい問題を林先生が逡巡するまま書かれており、それがより問題の厄介さを際立たせている。激弱なメンタルをなんとかしたい自分にとって、、それが病と言われるとどうかと考えてみると…色々な意味で示唆に富む刺激的な内容で大変面白かった。2012/10/03
fuchsia
3
出版社変わったせいか、扇情的なタイトルや惹句が少なめになっております。しかし、著者の正しい知識を知らしめて本当に苦しんでいる人の救済を望むメッセージは変化なし。しかしながらそれさえも「治療のバブル」へ安易につながってしまう現在の心療内科バブルは一種社会問題なのかもしれぬ。2010/12/27
yuka
3
語弊があるかもしれないけれど、「心の病」で得られる特権に対して微妙だわと思っていただけに、ちょっとすっきり。本当に辛い人が困らないためには、中途半端な知識で心の病を語らないことが大事なのかも。2010/07/30
pyonko
2
難しい問題。光が当たるようになったことで、前よりも精神科、心療内科に通いやすくなった。しかしそのことによる弊害を作者は指摘する。本書ではうつ、アスペルガー、アルコール依存症、PTSDについて述べられている。アスペルガーについては判断が難しいと思った。どこまでが個性でどこからがアスペルガーなのだろうか。もう少し詳しく見て行きたい。2014/09/25