出版社内容情報
草創期から2000年までの包括的研究書。アンジェイ・ワイダやクシシュトフ・キェシロフスキは翻弄されつづけてきたポーランドの歴史と寄り添いながら、一体何を描こうとしたのか。映画表現の芸術性に視点を置いて、ポーランド劇映画の魅力と百年の歴史を詳述した本邦初の映画史。映画題名索引・人名索引約1700件、関連スチール写真約160点を収録。精選フィルモグラフィも充実。映画輸入業者・配給会社、図書館、映画専門機関、研究者・評論家にとっては必携書。
著者より日本の読者に宛てて
謝 辞
▼▼▼▼
【プロローグ】
草創期から二〇〇〇年までの包括的研究書/政治的・教育的役割を果したポーランド映画/研究資料の多くが現存しない一九三九年以前、芸術性を疎んじた共産主義国家時代/本書における「ポーランド国民映画」の定義/本書の内容構成と時代区分
▼▼▼▼
【第1章】トーキー以前のポーランド映画
ポーランド最初の劇映画「愉快な男、帰る」/ポーランド映画最初のスター俳優、アントニ・フェルトネル/愛国映画というジャンル/文学作品の映画化/デンマーク・メロドラマの影響/イディッシュ映画
スフィンクス社(Sfinks)
多くのスター女優を誕生させた支配人ヘルツ/愛国的テーマとメロドラマで市場開拓
ポーランドの映画スターたち ポラ・ネグリとヤドヴィガ・スモサルスカ
ドイツで活躍し、その後ハリウッドに渡ったネグリ/象徴的なポーランド女性を演じたスモサルスカ/大ヒットした恋愛物語「ハンセン病患者」
一九一八年以後の映画産業
経営危機に陥った映画館/隆盛を誇るアメリカ映画、上映されなかったソヴィエト映画
愛国映画
愛国精神の伝統を描いた「歴史もの」の役割/画家グロトゲルの影響を帯びた「大暴風」/愛国的要素とメロドラマ的要素の結合/ドイツ映画とアメリカ映画の影響
文学作品の映画化と個性的スタイル
ポーランド文学の映画化/ビェガンスキの登場と監督の世代交代
ポーランドにおける初期映画理論・映画評論
マトゥシェフスキの映画論/最初に影響を及ぼしたのはドイツの映画理論/「フォトジェニー」の概念を広めたトルィスタン/カロル・イジコフスキ著『第十の詩神』
▼▼▼▼
【第2章】一九三〇年代のトーキー映画時代
最初のトーキー上映は一九二九年――吹き替えか字幕か/ポーランドで最初に作られたトーキー/映画産業の中心地ワルシャワ――スターを演じた舞台俳優たち/無声映画の佳作「白い軌跡」/「宿命の女」イナ・ベニタの出世作「放浪者」
◆一九三〇年代の愛国映画
愛国映画の典型例「シベリアへ」/愛国メロドラマの成立条件は歴史的事件と悲壮感/観客を魅了した「歴史・伝説・風景」描写/名声を確立したレイテス監督の愛国映画
◆コメディ
三〇年代半ばにコメディがブレイク/人気コメディ俳優、アドルフ・ディムシャ/成功したミュージカル・コメディ「忘れられた旋律」
◆メロドラマ
人気の鍵は万国共通の通俗性/メロドラマの中の女性/当たり作、文芸作品
◆新しい感性 映画団体「スタルト(START)」
芸術映画を推進する「スタルト」の設立/写実性・社会性を追求したフォルト監督/映画作家組合製作の社会派映画/名女優ヴィソツカの演技と、実験的手法に富んだ「ヴィスワ川の人々」
イディッシュ映画
▼▼▼▼
【第3章】ポーランド映画は誰の夢か(第二次世界大戦後の映画とポーランド国民の帰属意識の政治的構築)
ドイツ占領下の上映状況/戦時下の映画人
◆地政学的状況
ソ連化、単一民族化した戦後のポーランド/帰属意識再生の役割を担ったローマ・カトリック教会
◆映画産業における連続性の喪失
戦前映画の否定という新たな出発/映画産業の国有化と、「フィルム・ポルスキ」や「ウッチ映画大学」の誕生
◆戦後の最初の映画
戦後ポーランド映画の第一作「禁じられた歌」/ホロコースト映画の先駆作「アウシュヴィッツの女囚」/反ユダヤ感情も織り込んだフォルト監督の「境なす通り」/政治性の無さで人気を博したコメディ「宝物」
▼▼▼▼
【第4章】スターリン主義映画の手法(社会主義リアリズムの映画)
推進された社会主義リアリズム路線/市場を占有した共産圏映画
◆社会主義リアリズムの映画
古典的作品「二つの作業班」と「明るい野原」/ポーランド初のカラー映画「マリエンシュタットの冒険」/伝記映画「勝利の戦士」と「若き日のショパン」
◆社会主義リアリズムの登場人物
図式的であった「望ましい主人公」像/「ワルシャワ遠からず」に見る、新体制の体現者/女性と男性の関係はどう描かれたか
◆社会主義リアリズム教義の没落
ネオレアリズモ運動の影響/カンヌ映画祭最優秀監督賞を受賞した、フォルト監督の「バルスカ通りの五人組」/写実性を重んじた、巨匠カヴァレロヴィチ
◆「総括映画」
「バラ色の現実像」の正体を追及/「十月の春」を描いた、ムンク監督の「鉄路の男」
◆結 論
▼▼▼▼
【第5章】ポーランド派再訪
◆ポーランド派現象
「ポーランド派」の発生時期と終焉時期/多岐にわたって解釈される主要テーマと形式上の特質/同時代に目を向けた新世代の登場
◆映画産業の組織変化
映画製作プロダクション制度の導入/映画館、内外上映作品数、動員観客数/数々の国際映画賞を受賞
◆様々な影響
ネオレアリズモの影響とワイダ監督の「世代」/社会主義リアリズムの反動としての写実性/共産主義体制批判に通じた「黒いリアリズム」の諸作品/異彩を放つ、「輪結び」の監督ハスの表現主義
◆第二次世界大戦
「ワルシャワ蜂起」史観における多様性/ワルシャワ蜂起を描いた、ワイダ監督の出世作「地下水道」/特異な歴史観に根ざして表現した、ムンク監督「エロイカ」と「やぶにらみの幸福」/ワイダ監督の「灰とダイヤモンド」/クツ監督の「勇猛十字勲章」「訪問者なし」「列車の中の人々」/戦争と占領のテーマを扱った諸作品
◆戦争以外のテーマ
「ポーランド派」における多様性/史上最大の観客を動員したフォルト監督の「鉄十字軍」/フミェレフスキ監督の喜劇「エヴァは眠りたい」の成功/数々の賞を受賞した、カヴァレロヴィチ監督の「夜行列車」と「尼僧ヨアンナ」/初めてアカデミー賞にノミネートされた、ポランスキ監督の「水の中のナイフ」
◆「ポーランド派」の終焉
強化される検閲/党中央委員会事務局の「決議」/徐々に力を失っていった「ポーランド派」映画
▼▼▼▼
【第6章】一九六五年から七六年までの、文学作品の映画化、私的な映画、通俗映画
「小康状態」下における映画製作プロダクションの再編成/観客動員数、映画館数の推移/映画人口の減少、テレビ映画の映画化
◆文学作品の映画化
映画が政治的議論の対象とされる伝統/ハス監督の映画世界/シェンキェヴィチ原作映画など、小説の映画化
◆アンジェイ・ワイダ監督の映画(一九六九―七六年)
自己内省的な表現主義映画「すべて売り物」/国民的文学作品の映画化
◆戦争体験
「ポーランド派」的な作品/ソ連の大作手法で作られた作品/占領下の日常生活を描く/野心作
◆「第三のポーランド映画」
「第三世代」の登場/異彩を放つスコリモフスキ監督とザヌスィ監督/主な新進監督/七〇年代初頭に登場した若手監督
◆カジミェシュ・クツ監督の生地シロンスク
写実的・実験的な作品を発信するクツ監督/〈シロンスクもの〉三部作
◆コメディ
不条理をユーモアとテンポで揶揄、諷刺/人気作「航行」
▼▼▼▼
【第7章】「保護色」と「麻酔なしで」(「不信の映画」、「連帯」時代、そしてその後)
理想と現実の不一致、公式文化と反体制文化の混在/「モラルの不安の映画」、「不信の映画」の登場/現実を鋭く描いたドキュメンタリー映画や劇映画/「不信の映画」の監督の作品とその特徴/「不信の映画」の俳優たち
◆「連帯」時代
ホダコフスキ、ザヨンチュコフスキ共同監督の「労働者たち’80年」、クツ監督の「ひとつのロザリオの数珠玉」/ワイダ監督の「鉄の男」/ホラント監督の「熱病」「孤独な女」、ジェブロフスキ監督の「白昼」/キェシロフスキ監督の「偶然」「短い労働日」
◆同時代との関わりが薄い映画
文学作品の映画化/歴史映画、歴史叙事詩/バレヤ監督の人気コメディ/「文化を省察する映画」/シュルキン監督の近未来映画作品/政治に言及しなかった秀作
◆戒厳令下の映画、そしてその後
深まった「我々」と「彼ら」の溝/消える体制批判の映画、人気を博した娯楽作品/大作、野心作/文学作品の映画化/カトヴィツェ映画大学の設立
▼▼▼▼
【第8章】戦いのあとの風景(民主主義の回復)
映画産業 国家の独占事業から自由市場へ
独立系プロダクションによる製作/「お蔵入り」映画の公開/映画産業の民営化と、ハリウッド映画に対する国の保護策
◆「ベルリンの壁」崩壊後の映画人
単なる娯楽以上のものと見なされてきた映画芸術/政治的検閲から経済的検閲へ――求められる「新しい声」の発見/苦悩する映画人
◆現代史の清算
新しい思考方法の模索――「〈自由〉という名の映画館からの逃亡」の成功/現代史を問い直す諸作品/光を放ちつづけるクツ監督
◆コメディ
失敗作、成功作/諷刺劇、悲喜劇
◆九〇年代以降の私的映画
コンドラテュク監督の作品世界/「露天商」に見る、バランスキ監督の詩的表現世界/多作監督コルスキの作品世界
◆女性映画監督
ケンジェジャフスカ監督のデビュー作「烏」/将来を期待されるコトラルチク監督/ワザルキェヴィチ監督の「白い結婚」/活躍するサス監督
◆クシシュトフ・キェシロフスキ
ポーランド的な枠を超えた作品群/全一〇話で構成された半ドキュメンタリー作品「デカローグ」/「分身」をテーマにした「ふたりのヴェロニカ」/モラルのジレンマを描く「トリコロール」/キェシロフスキに寄り添う映画を作るシュトゥル監督
▼▼▼▼
【第9章】ポーランド映画におけるスターリン主義像
政治映画に関心を示さないポーランドの大衆/ハンガリー・ロシア映画界におけるスターリン主義時代の回顧
抑圧されたものの回帰 「大理石の男」とその後
スターリン主義否定の先駆的映画「大理石の男」/ワイダ作品から刺激を受けた体制批判の映画
◆スターリン主義をめぐる現代映画
フィディク監督の「金日成のパレード」/スターリン主義時代を生き抜いた人々を描いた諸作品
◆図像法
若い監督によって創られた典型的映像/滑稽でグロテスクな映像素材としての全体主義
◆結 論
▼▼▼▼
【第10章】戦後ポーランド映画におけるホロコーストの記憶とユダヤ人像
◆戦後初期ポーランド映画におけるユダヤ人像
ユダヤ文化が消し去られてしまった今日のポーランド/多くの場合、脇役であったユダヤ人/ユダヤ人が登場する注目すべき作品
◆「哀れなポーランド人がゲットーを見る」
「ショアー」に対する評価/「民族の記憶」を問題にしたブウォンスキのエッセイ/シュチピョルスキの小説「美しきザイデンマン夫人」/ユダヤ・ポーランド関係を扱った民主化後の劇映画
◆ワイダ監督の「コルチャク先生」と「聖週間」
コルチャクの受難と伝説を描く/ポーランド人のホロコースト体験を考察した「聖週間」
◆キヨフスキ監督の「〈彼女〉の存在」
夫婦の愛を阻む「壁」の存在/三角関係を扱ったメロドラマ
◆ブルィルスキ監督の「デボラ」
絶望感を演出/ホロコーストを利用したにすぎない失敗作
◆ズィルベル監督の「マリアとの別れ」
ボロフスキの古典的短編に新たな解釈を示す/「壁」をはさんだ二つの世界を描く
◆ウォムニツキ監督の「そしてこの森だけが」
歴史に翻弄された一般人を描く/同時代のジレンマを反映したリアリズム
◆一九六八年という年
若者の目を通して六八年の政治状況を再構成/六〇年代を懐古する、ピヴォヴァルスキ監督の「三月のアーモンド」
◆結 論
ドイツ軍の映像記録を利用したドキュメンタリー映画/ユダヤ文化を取り戻す試み
▼▼▼▼
【第11章】アメリカ風ポーランド映画
かつてはまともに扱われなかったジャンル映画/〈民警もの〉という教育的作品
◆一九八九年以降のポーランド・アクション映画
ポーランドの現実に持ち込まれるハリウッド調/興行成功部門になったアクション映画/タブーになっている「芸術」という言葉/テレビの人気シリーズもハリウッド調/タブーを描く――「無届外出」と「クロル」
◆パシコフスキ監督の「ポリ公」
演出はアメリカ的、背景は過渡期のポーランドそのもの/主人公は秘密警察の警部補フランツ/評論家や映画人の「ポリ公」考/「ポリ公2」も成功した/カリスマ的スター、ボグスワフ・リンダ/ダーティハリーばりのヒーロー、フランツの誕生/男気の称揚と性的対象としての女性像
◆マフルスキ監督の「デジャ・ヴュ」
世界中の映画を引用して構成/同監督の「ガール・ガイド」について
◆最近のアクション映画
政治や日常生活の描写を切り離しては成立しえない/アメリカ・ジャンル映画のイミテーションとも言える「夜のグラフィティ」と「若き狼たち」/ポスト共産主義の問題を伝える「父の法」
▼▼▼▼
【エピローグ】
二一世紀の入り口で、厳しい製作環境に揺れるポーランド映画界/芸術としての映画の将来は……/はたして映画産業界の構造的変革はあるだろうか
【日本語版への増補】二〇〇一年以降のポーランド映画
新しい欧州の現実の中で――民族アイデンティティに呼応する古典の映画化/二〇〇二―二〇〇五年における話題作や新人作品
●主要参考文献
●精選フィルモグラフィ(一九〇二―二〇〇一年)
●注 釈
【訳者あとがき】
●凡 例
●映画原題表記一覧
●人名原語表記一覧
●人名索引
●映画題名索引
ポーランド映画草創期から2000年までの包括的研究書。収載スチール160点、映画題名索引・人名索引1700件。映画研究者・評論家必携、図書館に必備の書。
内容説明
映画表現の芸術性に視点を置いて、ポーランド劇映画の魅力を分析。草創期から二〇〇〇年までの包括的研究書。
目次
プロローグ
トーキー以前のポーランド映画
一九三〇年代のトーキー映画時代
ポーランド映画は誰の夢か―第二次世界大戦後の映画とポーランド国民の帰属意識の政治的構築
スターリン主義映画の手法―社会主義リアリズムの映画
ポーランド派再訪
一九六五年から七六年までの、文学作品の映画化、私的な映画、通俗映画
「保護色」と「麻酔なしで」―「不信の映画」、「連帯」時代、そしてその後
戦いのあとの風景―民主主義の回復
ポーランド映画におけるスターリン主義像
戦後ポーランド映画におけるホロコーストの記憶とユダヤ人像
アメリカ風ポーランド映画
著者等紹介
ハルトフ,マレク[ハルトフ,マレク][Haltof,Marek]
1957年、ポーランド・チェシン生まれ。1980年、シロンスク大学卒。1989年、フリンダーズ大学卒。1995年、アルバータ大学大学院修了(Ph.D.)。2001年、大学教員資格(habilitacja)を取得(ヤギェウォ大学、ポーランド・クラクフ)。現在、北ミシガン大学助教授
西野常夫[ニシノツネオ]
1958年、和歌山県生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得満期退学。九州大学助教授
渡辺克義[ワタナベカツヨシ]
1960年、新潟県生まれ。東京大学大学院博士課程修了(博士、文学)。ワルシャワ大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。山口県立大学助教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
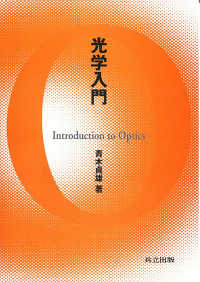
- 和書
- 光学入門






