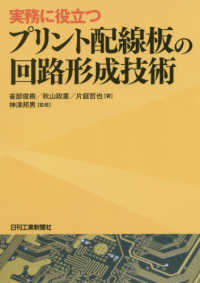内容説明
原発事故後の放射線・エネルギー問題を私たちが互いに伝え・学び合うための多様な教育実践。
目次
第1部 福島での授業・取り組み(福島第一原発事故とその後の教育―福島県教職員組合の取り組みと学校教育;放射線教育とどのように向き合うか―福島県での授業の実際;少女たちの声はきこえているか―福島県立相馬高校放送局の震災後の活動;原発教育において情報の公平性は確保されているか―人々の判断力・批判力を育む教育実践とESDとしての課題)
第2部 全国での授業・取り組み(「原発・エネルギー」を学生とともに考える―神戸女学院大学・石川康宏ゼミの取り組み;「原発事故」問題は教育プログラム化できるか―日本環境教育学会「原発事故のはなし」授業案作成ワーキンググループの取り組み;教材を通じた議論の場づくり―3・11と開発教育協会(DEAR)の取り組み)
第3部 座談会「福島第一原発事故を乗り越えるために―チェルノブイリ・福島・未来」
著者等紹介
阿部治[アベオサム]
1955年、新潟県生まれ。立教大学社会学部・異文化コミュニケーション研究科教授。同大学ESD研究所所長。専門は環境教育/ESD。筑波大学、埼玉大学などを経て2002年から現職。現在、日本環境教育学会会長、NPO法人持続可能な開発のための教育の10年推進会議(ESD‐J)代表理事などを務める。環境教育/ESDのパイオニアとして国内外における研究と実践に関わっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。