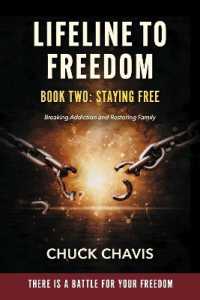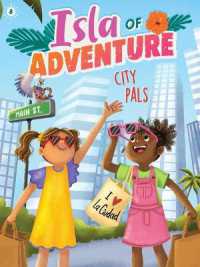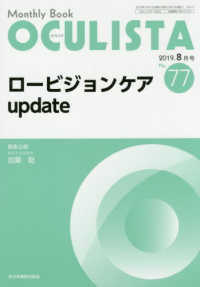内容説明
「教職員による教育の世界」であった学校に、心理臨床家=スクールカウンセラーが配置されて20年以上が経過した。この間、児童・生徒、そして学校が遭遇する問題は地域・ネット社会に広がり、「チームとしての学校」(文部科学省)のなかでスクールカウンセラーは今、連携を重視したバージョンアップが求められている。「システムズアプローチ」は、システムのアセスメント・参加・介入を統合的に行う臨床スキルであり、児童・生徒・保護者のカウンセリング、教職員へのコンサルテーションや学内研修、そして多機関連携と、多岐にわたる職務をスクールカウンセラーがこなし、さらに関係者の連携の相乗効果を期待できる、まさに「学校現場のためのアプローチ」である。好評初版を現代の学校環境にあわせて大幅改訂したスクールカウンセラー必携の書、待望の第2版。
目次
序章 システムとコミュニケーション―学校の「問題」と「解決」を見えるようにする
第1部 学校というシステムに参加する―「ジョイニング」について(学校というシステムの構造―小学校・中学校・高等学校の違い;ジョイニング―学校というシステムとの関係形成;ジョイニングの失敗)
第2部 連携のアレンジ―組織の橋渡し役として(学校における連携―総論;社会資源との連携は柔軟に・したたかに―外部関係機関を見立て、つながる;医療や行政機関との連携のお作法;スクールソーシャルワーカーについて)
第3部 コンサルテーションと地域援助―カウンセリング以外の仕事(コンサルテーション―相談できるシステムをつくる;システムズ・コンサルテーション―より協働的な取り組みをめざして;集団の問題のとらえ方―学級崩壊を例として;予防を視野に入れた援助―学内での会議と研修)
第4部 支援の留意点―システムズアプローチのバリエーション(本人に会わない保護者支援;本人にしか会えない本人支援;守秘義務と集団守秘;心理アセスメントの伝え方―テストの「力」を援助につなぐ;インターネット環境とSNSを視野に入れる;教員のエンパワーメント)
著者等紹介
吉川悟[ヨシカワサトル]
1958年滋賀県生まれ。1984年和光大学人文学部卒業。1986年大手前ファミリールーム職員。1988年システムズアプローチ研究所を設立し所長。1997年コミュニケーション・ケアセンターを設立し所長を兼任。2005年より龍谷大学文学部教授。日本家族療法学会元副会長、日本ブリーフサイコセラピー学会元会長。臨床心理士・公認心理師・家族心理士・医療心理士
赤津玲子[アカツレイコ]
1965年福島県生まれ。福島県浜児童相談所心理嘱託、神戸ファミリールーム、スクールカウンセラー、心療内科勤務。2012年龍谷大学文学部講師、2015年より龍谷大学文学部准教授。教育学博士。臨床心理士、公認心理士。日本ブリーフサイコセラピー学会理事
伊東秀章[イトウヒデアキ]
1984年大阪府生まれ。2014年龍谷大学大学院文学研究科博士課程修了。神戸ファミリールーム、スクールカウンセラー、精神科・心療内科などに勤務。2017年より龍谷大学文学部講師。博士(教育学)。臨床心理士、公認心理師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。