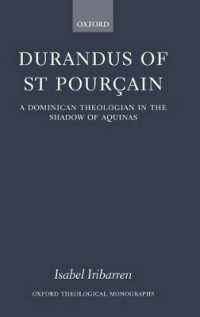出版社内容情報
死を目の前にした心理臨床家と精神腫瘍医(サイコオンコロジスト)が進めた終末期フィールドワーク/当事者研究の記録。
語られ,書かれた世界が人を規定する一方で,しかしそこで語り,書くことこそが世界を拓く。
2011年11月,食道がんでこの世を去った気鋭の心理臨床家・高橋規子と,精神腫瘍医(サイコオンコロジスト)小森康永のメール往復書簡を中心にまとめられた本書は,刻々進行するがんと「終末期」の時間を縦糸に,「当事者」が語ることの可能性を横糸に織り上げられた一つのナラティヴ実践である。
セラピスト・高橋規子の支援から協同(コラボレーション)へのラディカルな転換は,本書に収められた遺稿「友人Dの研究」にひとまずの結実をみるが,しかし自らの「終末期」の構築を通してその先へと読者を誘う。「言葉の力」への信頼が駆動するナラティヴというプロジェクトにおいて,死にゆく人に/は何ができるのか。本書はその試みである。
……ウチの業界では「言葉にならない思い」を大切にする傾向がありますが,それは「言葉が死んでいる」「言葉は重要ではない」からではなくて,「その人ならではの言葉が誕生する瞬間を言祝ぐ」ために違いないと,わたしは思っていました。それが「辞書にない言葉」であろうと「端からみれば陳腐な言葉」であろうと構わず,それまで関心を持ち合いながら暮らしてきた人々にとって「これはまさしくその人の言葉。借り物でも,お仕着せでもなく」と思わず納得の言葉が転がり出してきたとき,面接者は特に,共にここまですごしてきたことをとても意義深く感じるものではないかなと思います。……(「送信者:高橋規子2011年10月6日」より)
はじめに 3
第 I部 われわれはどこから来たのか 7
第1章 原家族原風景 9
第2章 原家族再訪 13
第 II 部 われわれは何者か 21
第3章 JAFT評議員の素顔に迫る 23
第4章 コラボレイティヴ・アプローチは,いかにして実践しうるのか 25
第5章 ナラティヴ・アプローチは,いかにして実践しうるのか? 45
第6章 「友人Dの研究」とその後 65
第 III 部 われわれはどこへ行くのか 87
第7章 2011年7月 89
7.11女木島の帰りに/7.14夏はいいな/7.19ディグニティ/7.26乳がんのこと
第8章 2011年8月 100
8.1名付けのこと/8.5アオザイの刺繍/8.12かのこやすらぎ会から/8.17危険思想/8.19ナラティヴ・メディシン/8.22読後連想/8.22アイデンティティと言説/8.22わたしもそうではないかと/8.24緩和ケア/8.24気管狭窄/8. 24ステント/8. 24主治医はだれ?/8. 31暴挙
第9章 2011年9月 125
9.2紡ぐ/9.12どうやって終わらせるか/9.14友人Dの研究/9.16外在化=解明/9.16いけ好かない言説/9.22言葉は生の側にある/9.22緊急入院/9.26頸の痛み/9.26記述形式/9.27パラレル・チャート/9.27カラー/9.28得策
第10章 2011年10月 142
10.4紡ぐへのリフレクション/10.4『……のために』を読んで/10.6患者vs.知人/10.6目の前の実践/10.6納得の言葉/10.11タイトルはあとで/10.11身内の集まり/10.12牽引/10.14秋田行き中止/10.14がんの痛み/10.18ホスピス入院/10.18症状緩和/10.19なにくれとなく/10.20絶対違う/10.24バロック/10.24現物支給/10.24謹呈/10.31呼称/10.31ホスピスっぽい亡くなり方
第11章 2011年11月 167
11.2お姫様願望/11.3日頃の生活ぶり/11.9私的か公的か/11.9親がほぼ毎日やって来ます/11.10「顔」/11.11修正稿
第X章 友人Dの研究 178
付録―書評 201
マイケル・ホワイト/デイヴィッド・エプストン『物語としての家族』 201
マイケル・ホワイト『セラピストの人生という物語』 203
マイケル・ホワイト『ナラティヴ・プラクティスとエキゾチックな人生』 205
小森康永『ナラティヴ実践再訪』 208
マイケル・ホワイト『ナラティヴ実践地図』 210
Marisa Silver“Night Train to Frankfurt, in “Alone With You””
内容説明
2011年11月、食道がんでこの世を去った気鋭の心理臨床家・高橋規子と、精神腫瘍医・小森康永のメール往復書簡を中心にまとめられた本書は、刻々進行するがんと「終末期」の時間を縦糸に、「当事者」が語ることの可能性を横糸に織り上げられた一つのナラティヴ実践である。
目次
第1部 われわれはどこから来たのか(原家族原風景;原家族再訪)
第2部 われわれは何者か(著者たちの素顔;コラボレイティヴ・アプローチは、いかにして実践しうるのか―筆者の、治療者としての思考のあり方を手がかりとした考察;ナラティヴ・アプローチは、いかにして実践しうるのか;「友人Dの研究」とその後)
第3部 われわれはどこへ行くのか(2011年7月;2011年8月;2011年9月;2011年10月;2011年11月)
第X章 友人Dの研究
著者等紹介
高橋規子[タカハシノリコ]
1986年学習院大学文学部心理学科卒業。民間相談所カウンセラーを経て、1995年カウンセリングルーム心理技術研究所開業。臨床心理士。日本家族研究・家族療法学会評議員、日本ブリーフサイコセラピー学会理事、サンタフェNLP/発達心理学協会認定プラクティショナートレーナー/マスターIトレーナー。2011年11月13日逝去
小森康永[コモリヤスナガ]
1985年岐阜大学医学部卒業。以後同大学小児科に在籍。鳥取大学脳神経小児科、メンタル・リサーチ・インスティチュート(MRI)等で研修。1995年名古屋大学医学部精神科へ転入。愛知県立城山病院を経て、現在愛知県がんセンター中央病院緩和ケア部精神腫瘍診療科。日本家族研究・家族療法学会評議員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たらこ
ポカホンタス
餃子