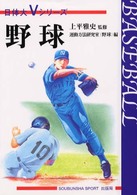内容説明
犯罪の歴史はそのまま人類の歴史である。古くは宗教的タブーから誕生し、近代にいたって社会的に禁止された行為として規定されるまで、犯罪は「最古の社会問題」であった。しかし、学問的対象として犯罪学が誕生したのはようやく前世紀末においてのことである。著者は本書において、個々の現象としての犯罪行為を通してトータルな人間理解を試み、犯罪学を人間科学として捉え直すことによる、新たな「犯罪精神病理学」の構築をめざしている。本書の大きな特徴は、暗殺や大量殺人、ストーカー犯罪、ハイジャック犯罪など従来わが国の犯罪学研究においてはあまり顧みられることのなかった分野や、最近顕著になりつつある話題性に富んだ主題が扱われている点である。また、著者は最近の少年犯罪の質的な変化に着目し、この変化を「自己確認型」非行・犯罪と規定、表現し、「空虚な自己」「のび太症候群」などの独自の鍵概念、用語を用いて、現代青少年の心理的背景を分析し、現在頻発する犯罪と狂気を鋭く考察する。
目次
序編 犯罪精神医学の方法論(はじめに:「司法精神医学」と「犯罪精神医学」、「犯罪精神病理学」;犯罪学方法論の歴史的考察:新しい「犯罪学」と「犯罪精神病理学」の構築に向けて―自然科学と人間科学の方法論論争のドラマ)
1 分裂病、パラノイアと犯罪(パラノイア犯罪と迫害妄想者の類型分類:「間接告発症」―起訴前鑑定一〇年間の分析;大量殺人の犯罪学的研究;暗殺の精神病理と異常心理;慢性妄想病の言語論的アプローチ―実子殺人の一鑑定例をめぐって)
2 躁うつ病・覚醒剤依存・自閉症と犯罪(躁うつ病と犯罪;覚醒剤依存と犯罪―理論モデルと他の薬物依存および精神分裂病犯罪との比較;自閉症者の犯罪と精神鑑定)
3 現代の犯罪と非行(「自己確認型」非行―ナイフとパソコン;子どもがキレる理由と背景―「空虚な自己」と「超のび太症候群」;ストーカーの精神病理;多重人格と犯罪精神医学―もう一つの人格は犯罪を起こすか? ほか)