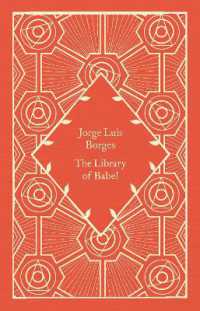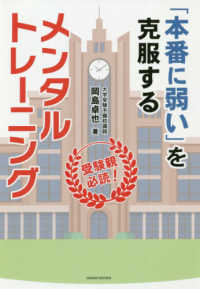出版社内容情報
人々の様々な活動を地理空間技術によって支援する参加型GISについて解説し、災害・福祉など様々な分野での応用事例を紹介。
序章 参加型GIS(PGIS)の展開
第?部 PGISの理論
1 PGIS研究の系譜(その1)
2 PGIS研究の系譜(その2)
3 ジオデザインにおける市民参加の可能性
4 地元学とPPGIS
5 地理空間情報のクラウドソーシング
6 カウンターマッピング
7 地理空間情報の倫理
第?部 PGISを支える技術と仕組み
8 PGISとオープンガバメント・オープンデータ
9 PGISの活動とオープンソースGIS・オープンな地理空間情報
10 PGISのハードウェア
11 PPGIS教育ツール
12 PGISのための人材育成
13 先住民マッピング
第?部 PGISの応用
14 クライシスマッピング
15 ハザードマップと参加型GIS
16 放射線量マッピング
17 通学路見守り活動における地図活用
18 地域づくり:能登島の事例
19 市民参加型GISによる祭礼景観の復原
20 ICTプラットフォームによる市民協働型の課題解決
21 子育てマップと当事者参加
22 ボランタリー組織による地図作製活動を通じた視覚障害者の外出支援
23 介護カルテ:西和賀町の事例
24 位置情報とARを用いたまち探検
25 大学教育と参加型GIS
26 海外におけるオープンガバメント・オープンデータの実践事例
27 日本におけるオープンガバメント・オープンデータの実践事例
若林 芳樹[ワカバヤシ ヨシキ]
今井 修[イマイ オサム]
瀬戸 寿一[セト トシカズ]
西村 雄一郎[ニシムラ ユウイチロウ]
目次
参加型GISの展開
第1部 PGISの理論(PGIS研究の系譜;ジオデザインにおける市民参加の可能性;地元学とPPGIS ほか)
第2部 PGISを支える技術と仕組み(PGISとオープンガバメント・オープンデータ;PGISとオープンソースGIS・オープンな地理空間情報;PGISのハードウェア ほか)
第3部 PGISの応用(クライシスマッピング;ハザードマップと参加型GIS;放射線量マッピング ほか)
著者等紹介
若林芳樹[ワカバヤシヨシキ]
1959年佐賀県生まれ。1986年広島大学大学院文学研究科博士前期課程単位取得退学。現在、首都大学東京都市環境学部教授。博士(理学)
今井修[イマイオサム]
1948年兵庫県生まれ。1974年東北大学理学部地球物理専攻修士修了。(株)パスコ、NPO国土空間データ基盤推進協議会、東京大学空間情報科学研究センターを経て現在、(有)ジー・リサーチ代表取締役
瀬戸寿一[セトトシカズ]
1979年東京都生まれ。2012年立命館大学文学研究科人文学専攻博士課程後期課程修了。現在、東京大学空間情報科学研究センター特任講師。博士(文学)
西村雄一郎[ニシムラユウイチロウ]
1970年愛知県生まれ。2003年名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。現在、奈良女子大学人文科学系研究院准教授。博士(地理学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
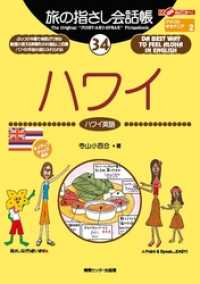
- 電子書籍
- 旅の指さし会話帳34ハワイ