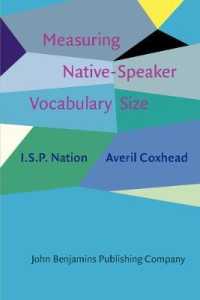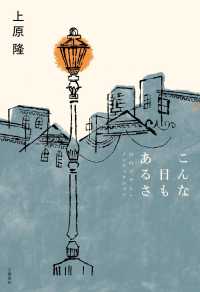- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
目次
ペーパー・マットの上の虎(ヴラド・ゴズィッチ)
理論への抵抗
文献学への回帰
ハイポグラムと記銘
読むことと歴史
結惑―ヴァルター・ベンヤミンの「翻訳者の使命」
ダイアローグとダイアローグ性
ポール・ド・マンとの対話(ステファノ・ロッソ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ecriture
12
芸術にとって批評理論とは敵なのだろうか。そもそも理論とは何なのだろうか。猫を虎と錯覚し、または猫を鼠だと錯覚するような歪曲、誤解がそこには潜んでいる。理論への抵抗、それは不可能なものである。なぜならば、言語を言語化したものである理論自体が理論へつねにすでに抵抗しているからからだ。しかし、仮にも体系化されている以上、大学において教授することもできるし権威的にみなされることもできる。理論の語源である「テオレイン」にあたればそれも不思議ではない。理論とは何か。あまりに鮮やかな回答がここにある。2010/09/21
なっぢ@断捨離実行中
9
教育目的の論文に『理論への抵抗』と題するこのKY精神どうよ。これでも本人は至って真面目らしい、というかとても謙虚で禁欲的ですらあるのが逆に怖い。本書で特に印象に残ったのは「デリダは哲学者であり、自分は文献学者」との言だ。ベルギーという周縁に生まれた彼には理論一般が胡散臭く、抑圧的に映ったのではないか。理論を誰も所有しえないテクストとして解放することがドマンの核心だとすれば過去に親ナチ的な記事を書いたかどでドマンや脱構築を葬り去ろうとするのは二重に不当だろうと柄谷の本を読みながら思った(書評になってない)2017/03/21
akuragitatata
3
理論への抵抗。それは言語の非人間性の肯定であり、恐怖である。ド・マンとエイブラムスのやりとりがある後段ではそういうことがちらりと伺える。ド・マンの語り口はなかなかに辛辣で高度だが、ここで論じられてきた修辞技法とも記号論とも取れないような詩的な飛躍。言語の論理的な跳躍に作者の声を読み取ってしまおうという安直さや記号論的な意味の付与への抵抗は、ド・マンが脱構築を通じて実現しようとする論なのだ。ベイカー的な文学(部)の脅威ばかりを取り上げる浅薄な10年代の人文学は、いまいちどこの絶対零度へ挑むべきである。2017/07/24
ちあき
3
文学理論の世界に大きな影響力をおよぼした碩学の死後まとめられた論集。気軽に手にとれる本ではない。自分の場合でいえば、名前すら知らなかったリファテールについての論文はどれだけ理解できたのか自信がないし、質疑応答に登場する学者たちの言葉に至っては何を意図しているのかすらさっぱりだった。ただ、〈読む〉という営為にこだわりつづけるド・マンの姿勢はよくわかったし、感銘を受けた。とくに「結論」と題された文章が圧巻ともいえる読みごたえ。ここを味わうにはベンヤミンの「翻訳者の使命」は読んでおかないともったいないと思う。2013/02/28
放蕩息子
1
初読2013/03/31