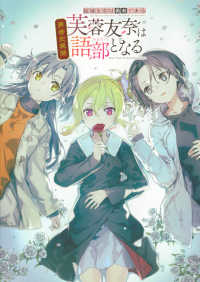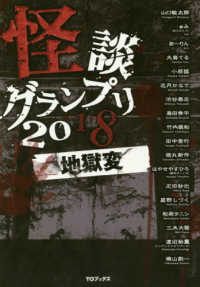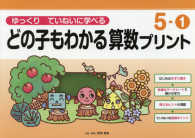内容説明
「勇猛果敢の眞実」ともいふべきものの自己証明の文学―と、三島由紀夫氏が絶賛したアンガウル玉砕島兵士の証言。二十倍にものぼる圧倒的な米軍との四十日間におよんだ“鉄と肉体”の凄惨な戦いを赤裸々に描き、南海の孤島に斃れた千百余名の戦友たちの“声なき叫び”をつたえる感動のノンフィクション戦記。
目次
二十倍の敵上陸す
複廓陣地の死闘
司令部テント突入計画
収容所での闘魂
昨日の敵は今日の友
英霊の絶叫
友情は海をこえて
著者等紹介
舩坂弘[フナサカヒロシ]
大正9年、栃木県に生まれる。昭和15年満蒙学校卒。16年、満州216部隊に入隊、19年、中部太平洋に参戦。21年、復員。その後、書店経営にあたり、大盛堂書店会長。南太平洋慰霊協会理事、全日本銃剣道連盟参与、東京都ユースホステル協会理事など数団体の要職につく。剣道六段教士、居合道練士、銃剣道練士。テキサス州名誉市民章を受ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
スー
22
電132不死身の分隊長といわれた最強の日本兵舩坂弘氏が書いたアンガウル島の激戦の体験記です。1200人が守るアンガウル島は2万人を超えるアメリカ軍に攻められ圧倒的な火力の前に為すすべなく後退し最終防衛の洞窟に籠り絶望的な戦いを続ける。倒れた戦友を助け励まし手当てする姿はここでは見られない、日本兵が攻撃するとすぐに艦砲射撃が始まり日本兵はたちまち肉片となり跡形も無く消えてしまう。生き残っても飢餓で倒れ水を求めた者は米軍の待ち伏せで次々と撃ち殺されていった。まさに地獄だった。2019/09/08
やじ
21
三島由紀夫氏の序文から凄い‥。昭和40年頃、剣道の先輩であった船坂氏が、大部の生原稿を道場に持って来られたそうだ。戦後二十年の間、船坂氏のなかを駆けずり廻っていた抑圧された叫び。三島氏の介錯に使われたのが、船坂氏から贈られた名刀「関の孫六」だったという。アンガウルのご英霊達の叫びを、私達は無心になって聞くべきだ。皆様のおかげで日本は守られました。感謝しかありません。今の日本は恥ずかしくて見せられませんが、不死身の船坂氏の負けじ魂を今こそ一人一人が持つべきだと思う。2019/03/13
びっぐすとん
20
同僚から借りた本。読むのが辛くなかなかページが進まなかった。阿鼻叫喚の生き地獄だった南方のアンガウル島で戦い、何度も傷を負いながら、信じがたい精神力と体力で生き長らえ捕虜となり、米兵にすら驚愕された元日本兵の手記。信じられないタフさだ。負傷、飢餓、物資不足の有り様は読むだけでも辛く、私なら早々に諦めるか発狂するだろうし、その方が幸せではないかとさえ思えてくる。人が人の命を奪う。理不尽に失われる命に対して何の感情も持たなくなる。戦争は狂気だ。個人間では敵味方の間でも友情を育めるのに、集団の心理とは恐ろしい。2022/07/08
こぺたろう
10
読了。平和に対する思いの言葉が、非常に重く感じられました。また、ペリリュー島との位置関係を再確認し、改めて小さな島だと思いました。米軍側との物量差を目の当たりにしたときは、衝撃だったろうなと想像。捕虜収容所で出会ったクレンショー氏との、戦後の交流を描いた章も、とても良かった。三島由紀夫氏との関係も。2022/01/26
モリータ
10
小学校高学年〜中学で(NF・架空)戦記を飽きるほど読み、今でも戦史や兵器、日本軍の局地的戦闘や戦術の勝利を見聞することに興味を持ちつつ、全体として非人道的・非合理的な(日本軍に限らない)戦争というものの実態を、前線のみならず、戦争に加わった多様な人々の視点、国内外の政治・経済・文化といった大きな観点からとらえなければならない(後者は勉強が足りないが…)と思う者にとって、特異な個人が華々しく戦ったさまが装飾過多の文章で綴られた本書は、エンタメとしてもミクロな戦史としてももはやいたましく、通読できなかった。2019/03/03
-

- 和書
- 土屋文明 - 短歌の近代