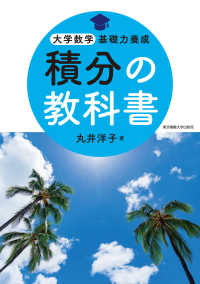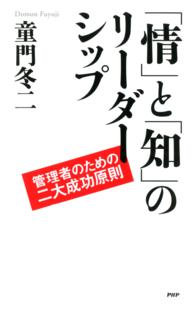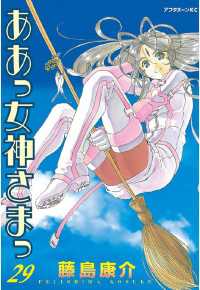内容説明
“和製メッサー”と呼ばれた日本で唯一の液冷エンジン戦闘機・飛燕―格闘性能を合わせもつ高速機として万能戦闘機の名を冠せられた傑作機。その美しい姿態に秘められた設計チームの苦悩と、実戦場での血と汗と涙の苦闘の数々を描き好性能を発揮することなく終末を迎えた悲しき生涯を捉えたノンフィクション。
目次
序章 台湾を襲った嵐
第1章 若きパイオニアたち
第2章 欧州の余波
第3章 「飛燕」飛ぶ
第4章 新鋭機の活躍
第5章 銃後の戦い
第6章 五式戦の登場
著者等紹介
碇義朗[イカリヨシロウ]
1925年、鹿児島生まれ、東京都立航空工業学校卒。陸軍航空技術研究所をへて、戦後、横浜工業専門学校(現横浜国立大学)卒。航空、自動車、鉄道などメカニズムと人間のかかわり合いをテーマにドキュメントを発表。航空ジャーナリスト協会会員。横浜ペンクラブ会員。自動車技術会会員。カナダ・カーマン名誉市民(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Cornelius
27
この本は、三式戦闘機「飛燕」がいかにして誕生し、苦闘し、終焉を迎えたかを記した本だ。設計者土井武夫氏と川崎航空機の歩みを追いながら、川崎で作られた飛行機のことなども書かれている。また、飛燕につきまとったエンジントラブルや前線での様子もところどころ記されていて、バランスのよい構成になっていた。文章も読みやすかった。2016/06/12
roatsu
13
薄幸の名機・飛燕の誕生に至る技術的背景と託された技術的狙い、数々の操縦者の奮闘、設計者たる土井武夫技師を筆頭に敗戦まで携わった数多関係者達の証言・記録を織りなして綴る秀逸なドキュメント。冒頭、台湾沖航空戦において本機を遺憾なく使いこなし米艦載機群に勝ち越した田形准尉達の奮戦はいつもながら手に汗握る。独国技師から指導を受けた川重軍用機部門が同国の影響を強く受けて発達する過程や、天才・土井技師の実用を踏まえた設計姿勢と軍方針を先読みした政治的周到さに改めて驚嘆する。堀越二郎より注目すべき天才はこの方だろう。2016/08/11
Machida Hiroshi
6
本書は、これまたエンジンに恵まれなかったものの、流麗な機体にして高速度と高戦闘性能を誇った飛燕という戦闘機に関わった技術開発陣、整備士、操縦士、それぞれの苦闘を描いたノンフィクション戦記です。飛燕もまた日本の工業技術の低さに泣いた機体でした。ダイムラーベンツのエンジンDB601を国産化したのですが、工作精度やオイルの品質が悪く、オイル漏れはするし、ローラーベアリングが良く焼き付きを起こしたり、ラジエーター、燃料噴射器なども良く壊れるなど、故障のデパートだったようです。この工業力で良く戦争を始めたものです。2017/04/21
χ
5
飛燕ってこんなにかっこ良かったのか。日本の戦闘機としては異色の形と性能、頑丈さ。鼻がとんがってるのがいい。液冷から空冷エンジンにかえても性能が落ちなかったのは設計が優れていたからなんだなあ。1冊の本で丹念に取り上げられてるのを読んでやっとよさがわかった2014/01/17
99t
3
優れた設計の飛行機だったものの、エンジンのトラブルが多く、本来の能力を発揮できなかった。生産現場の水準の低さに泣いた飛行機だった▼陸軍と海軍の不調和など、組織の弱さが浮き彫りにされている。2012/04/12