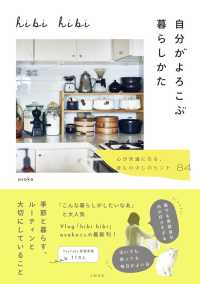内容説明
山陰山陽の枢要地松江。堀尾・京極氏のあと松平氏、大火水害凶作で財政窮迫、七代治郷は殖産振興に努め、財政再建。のち不昧と号し、茶道・書画・和歌などで名を残した優雅の藩の物語。
目次
第1章 堀尾・京極氏までの出雲―古代出雲の地に堀尾氏三代が城下町を築き、京極忠高が手を入れる。(律令制時代から中世の出雲;堀尾吉晴・忠氏父子の富田入城;堀尾吉晴・忠治の時代;京極氏の入封)
第2章 松平氏の治世が始まる―親藩として山陰・山陽の要に配置された松平氏は、維新まで、十代続く。(松平直政の松江と江戸での足跡;松平家二代綱隆の治世;祖先を敬い、松江を愛した綱近;藩の台所事情と世情)
第3章 藩財政の窮乏と改革―宗衍の努力は報われず、治郷こと不昧の代に好転の兆しが見える。(改革の頓挫を余儀なくされた宗衍;財政立て直しに尽力する治郷;お茶の殿様「不昧」公)
第4章 幕末から明治にかけての苦渋―開明的な藩主が出現するも、維新後は新政府への対応に悩む。(文化・文政の爛熟期;最後のお殿様・定安;維新前後の松江藩)
著者等紹介
石井悠[イシイハルカ]
1945年、島根県松江市生まれ。大阪府・島根県の中学校教員、島根県教育委員会(文化財行政)などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
駅長ポニョ
0
山陰の親藩・松江藩。 堀尾・京極氏が基礎を築き、真田幸村が称えた越前松平家の直政が入ります。 名君・松平不昧の下、文化都市・松江が育っていきます。 外界の隠岐に接しているためか、軍備の西洋化が進んでいる様子が印象的でした。2018/05/08
ポニョ駅長
0
前日にブラタモリがあってたので、興味が湧き再読。 築城者・堀尾吉晴が息子の遺志を継いで山陰随一の城下町の基礎を築く経緯が胸を打ちます。 その後は越前松平家の領地になり、文化に貢献した不昧公や意外と先進的だった幕末と、親藩にしては興味深い藩です。2015/08/02
Davis MickelsonⅢ世
0
江戸時代の歴代松江藩主による治世についてまとめられている。本書によると松江藩は度々大規模な洪水に悩まされていたようで、正直なところ松江という湿地帯に城下町を作ったのは結構な失敗だったのではないかと思ってしまった。一番興味深かったのは、松平不昧が茶器を買い込んで藩の経営を傾かせたという広く言われている説に対しグラフを用いて反論している点である。不昧の個人的趣味による出費の割合は少なく、また田沼家の失脚や江戸の冬木家の破産に伴い市場に流れた名物を割安で買い込むなどの工夫があったという。