内容説明
食べる前に読みますか?料理する前に読みますか?調理法・食材から見たスペイン料理の成り立ち。
目次
第1部 調理法から見るスペイン料理の成り立ち(オーリャ;アサード;カスエラ;ポストレ)
第2部 食材から見るスペイン料理(アセイテ(オリーブ油)
オルタリサ(野菜)
アロス(米)
レグンブレ(豆類)
ウエボ(卵)
ペスカード(魚) ほか)
著者等紹介
渡辺万里[ワタナベマリ]
学習院大学法学部卒。1975年よりスペイン・マドリードのピラール・サラウ女史その他の指導を受けてスペイン料理を学ぶ。1989年、スペイン食文化の紹介を目的として東京目白に「スペイン料理文化アカデミー」を開設。以来、執筆、講演、後進の指導などの活動に携わっている。早稲田大学文化構想学部非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
354
この前に読んだ『修道院のウズラ料理』は紀行的な要素を多々持っていたが、本書はより本格的なスペイン料理の解説書。料理を通して、スペインの文化や歴史が語られる。そもそもそうした背景なしには、スペイン料理を語ることができないとも言えるのだろう。本書は一般啓蒙書だが、研究書といっても差し支えないレベルなのではないかと、素人の私などは感嘆する。全15章よりなるが、前半は調理法、後半は食材に焦点をあてて語られる。スペイン料理というのは、なんとも奥深く、また豊かな地方性を有していることかと、またまた感嘆するのである。2021/12/29
たまきら
35
すごく面白かったけれど、ああ、カラーだったらなあ…!なんて思いながら。スペインが受けた侵略の歴史、かたくなに変わらない食の嗜好。その食文化がどのように生まれ、多少は変化しつつも現代に受け継がれてきているのだ、ということが章を読んでいくうちにじんわりしみてきます。南米の食材がいち早く受け入れられてきた背景には正直胸が痛みました…。2021/11/25
あか
2
スペイン料理の文化史。昨今のバルの隆盛のおかげで、アヒージョや簡単なタパスなどの居酒屋メニューはすぐに思いつくようになったが、そういえばスペイン料理の特徴ってなんだろう? と考えた時、思いつかないことに気づいた。スペインの歴史に沿いながら、スペイン料理の変遷について手際よく解説している。そもそも各地の自治性が強く、地方料理はあってもそれを束ねる共通性は案外少ないこと、フランスと違い宮廷の持続が短く料理が洗練に欠くこと、レコンキスタと豚肉など、興味深いトピックが多く楽しめた。2017/04/03
taiyo
1
スペインの食について、文化や歴史の側面からも概説する意欲的な書。スペイン料理に携わる人は絶対に読む必要がある。2019/12/09
y_a
1
バルセロナに何度か訪れた後に読むと納得感と楽しさがすごい。そして次に行くのが更に楽しみになる。2019/05/30
-
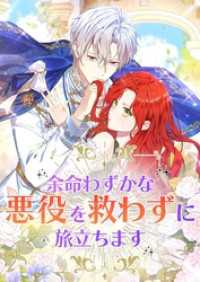
- 電子書籍
- 余命わずかな悪役を救わずに旅立ちます【…
-
![モーニング 2021年18号 [2021年4月1日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0977264.jpg)
- 電子書籍
- モーニング 2021年18号 [202…







