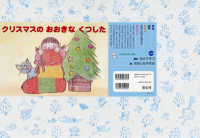- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
出版社内容情報
世界14か国で出版のベストセラーエッセイ、待望の日本版
屋根裏の改築依頼の電話から、施主への引き渡しまでの日々が、現役大工のクラフトマンシップ豊かなディテールとともに綴られる。建設業界の現状や、近しくも遠い国ノルウェーの人々の暮らし・働くことの誇りと喜びが、ユーモアあふれる率直な語り口から浮かび上がるシンプルなのに深いエッセイ。決して波乱万丈ではない健全な仕事人の物語。
内容説明
『あるノルウェーの大工の日記』は、屋根裏の物語である。屋根裏の改築依頼の電話から施主への引き渡しまでの日々が、職人技の豊かなディテールとともに綴られる。ユーモアを交えた率直な語りのなかに浮かび上がる、建設業界の厳しい現状やノルウェーの人々の暮らし、そして働くことの誇りと喜び。遠い北欧の国で紡がれた、現役の大工の手によるエッセイ。
著者等紹介
トシュテンセン,オーレ[トシュテンセン,オーレ] [Thorstensen,Ole]
ノルウェーのアーレンダールに生まれ、トロモイ島で育つ。25年以上の経験を持つ大工。現在はオスロ近郊のアイツヴォル在住
牧尾晴喜[マキオハルキ]
1974年、大阪生まれ。建築やデザイン関係の翻訳を手がけている。フレーズクレーズ代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
57
従兄弟が大工なだけに、いっそう身近に。読んでいて、とても気分が落ち着くのは、何故だろうと思う。それだけ、著者が、一生懸命でいい人だからだろう。人は、失敗するために生きているし、それを受け入れる、受け入れてくれる環境が大切。2018/06/09
fwhd8325
48
とても興味深いエッセイ。日本の職人とはスタイルが違うようだけれど、まじめで誠実であることの根本で通じているのかなと思いながら、楽しく読みました。ものを完成させるまでの過程が、面白いのはもちろんなのだけど、ひとりの職人としての言葉にも惹かれるものがあります。2018/01/05
おかむら
48
一人親方の職人さんによるリフォーム日誌。大工さんって腕のいいのは勿論ですが、仕事ってそれだけでなく、見積書の作成、他社との駆け引き、資材の調達、各職人の手配、工期の調整、施主との折衝、変更への対応、とやること盛りだくさん。ノルウェーの話だけど、日本でもたぶん近隣で評判のいい工務店ってこういう仕事の仕方をしてるのかなーと感服しました。職人が多少ボヤキも入りつつ基本気持ちよく働く楽しさが伝わってきて読んでて気分が良い! 施主一家も満足してたが私も満足だ! ノルウェーでベストセラーの翻訳だそうです。2017/11/22
ばんだねいっぺい
41
想像よりもずっといい本だった。立場上、見積書をもらうことが多いが、相当の時間を費やしていることを知り、申し訳ないと思った。とある一家の入札から施工完了までをドキュメンタリーとして追えるのが楽しい。屋根の構造、方杖、繋ぎ小梁、垂木など、興味が沸いた。職人と建築士の距離感の問題は何かに似ている。「喜びに弾む彼らの声を聞くのは、大工冥利に尽きる。」読者にとっては、この一語に尽きる。2021/02/03
チャーリブ
38
最近ノルウェー語を勉強しているので、ノルウェーがらみで読んでみた一冊だが、とても読み応えがあった。内容は、タイトル通りノルウェーのオスロ在住の大工さんの日記なのだが、その文章がすばらしい。簡潔にして明晰、機知に富んで、かつヒューマニスティック。建築現場の専門的な内容が多いのだが、半知半解でも自然と気持ちよく読まされてしまう。「現場で相手のことが一番よく分かるのは一緒に重荷を運ぶとき」といった現場の洞察は哲学的ですらある。職人たちが多言語化しているノルウェーの状況なども興味深かった。○2021/11/12
-

- 洋書
- FAT COP
-
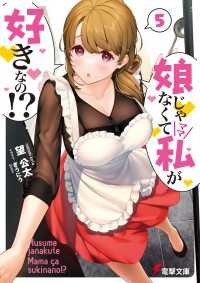
- 電子書籍
- 娘じゃなくて私が好きなの!?(5) 電…