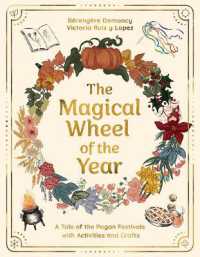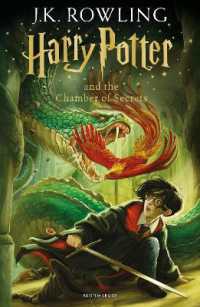出版社内容情報
江戸文芸の「花道」にあらわれた近世の世界認識
『平家物語』『太平記』『曾我物語』『義経記』といった軍記物語類は、浄瑠璃や歌舞伎といった演劇のみならず、浮世草子から読本に至る小説などにも多大な影響を与えている。本書では、西鶴・芭蕉・近松の諸作品から幕末の河竹黙阿弥の歌舞伎に至るまで、その特徴的な作品を幅広く取り上げてその影響を詳細に検討し、江戸文芸の「花道」にあらわれた近世の世界認識を提示する。
内容説明
『平家物語』『太平記』『曾我物語』『義経記』といった軍記物語類は、浄瑠璃や歌舞伎といった演劇のみならず、浮世草子から読本に至る小説などにも多大な影響を与えている。本書では、西鶴・芭蕉・近松の諸作品から幕末の河竹黙阿弥の歌舞伎に至るまで、その特徴的な作品を幅広く取り上げてその影響を詳細に検討し、江戸文芸の「花道」にあらわれた近世の世界認識を提示する。
目次
第1章 西鶴の義理批判―『武家義理物語』と幸若舞曲『満仲』
第2章 芭蕉の名所革命―『おくのほそ道』と『平家物語』『義経記』
第3章 松尾芭蕉と木曾義仲―『おくのほそ道』と『平家物語』
第4章 近松浄瑠璃と『平家物語』―『佐々木大鑑』を視座として
第5章 『義経千本桜』と『平家物語評判秘伝抄』
第6章 新田義貞の兜は何を意味しているのか―『仮名手本忠臣蔵』と『太平記』
第7章 反転する敵討―鶴屋南北と『東海道四谷怪談』
第8章 生命と貨幣―『三人吉三廓初買』と『曾我物語』
第9章 和歌から物語へ―「浅茅が宿」と『兼好法師集』
第10章 『平家物語』伝承の近世と近代―『小敦盛』をめぐって
著者等紹介
佐谷眞木人[サヤマキト]
1962年大阪市生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学院文学研究科国文学専攻博士課程単位取得。博士(文学)。現在、恵泉女学園大学人文学部教授。専攻は、中世・近世国文学、古典芸能史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。