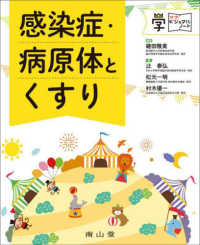出版社内容情報
▼啓蒙されるべき未成熟な理性は、いかにして自らを啓蒙するのか?
▼カント哲学がはらむ〈啓蒙のジレンマ〉を〈想像力〉を読み解くことで解決しようとする意欲作。
本書の目的は、これまで看過されてきた想像力(Einbildungskraft)の理論をその全体像において示し、カントのテクストにそくして「啓蒙の循環」という問題に対する方策を提示することにある。中間的な存在者としての人間の、やはり中間的な能力としての想像力に照明をあてることによって、カントの批判哲学を本来のダイナミズムにおいて提示しようとする試みである。
『判断力批判』のきわめて難解な、しかし豊かな記述には、完全な理性的存在者の王国でもなければ、不完全な感性的存在者の結合でもない、その中間としての文化的共同体の可能性が潜在している。それは理性と感性だけでなく、想像力と感情をそなえた人間が歴史的に創造する人工物であり、啓蒙の拠点である。
内容説明
本書の目的は、これまで看過されてきた想像力(Einbildungskraft)の理論をその全体像において示し、カントのテクストにそくして「啓蒙の循環」という問題に対する方策を提示することにある。中間的な存在者としての人間の、やはり中間的な能力としての想像力に照明をあてることによって、カントの批判哲学を本来のダイナミズムにおいて提示しようとする試みである。『判断力批判』のきわめて難解な、しかし豊かな記述には、完全な理性的存在者の王国でもなければ、不完全な感性的存在者の結合でもない、その中間としての文化的共同体の可能性が潜在している。それは理性と感性だけでなく、想像力と感情をそなえた人間が歴史的に創造する人工物であり、啓蒙の拠点である。
目次
序論
第1部 想像力と理論理性(綜合とは何か―「世界」の秩序をつくる;想像力と自己意識―「わたし」の意識をつくる)
第2部 想像力と実践理性(自律の構想―実践哲学の目指すもの;想像力と歴史哲学―理性の発展を跡づける)
第3部 想像力と『判断力批判』(美感的判断の構造―「想像力の自由」とは何か;想像力と感情―啓蒙の原動力を探る)
結論 想像力の哲学
著者等紹介
永守伸年[ナガモリノブトシ]
1984年生まれ。京都市立芸術大学美術学部講師。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門は18世紀ヨーロッパ哲学のほか、信頼研究、障害学、現代倫理学など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bevel