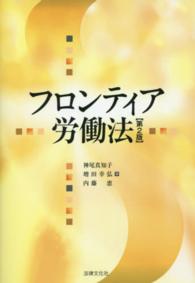出版社内容情報
本書は「持続可能な発展」の「環境」・「経済」・「社会」、これらの3要素を複合的に用いて、「共生社会」の実践を横断的に描く。
▼アジアという多様な自然環境、政治制度、宗教文化が集まる地域空間において、「持続可能な発展」はどうあるべきか?
「持続可能な発展」は、単に自然や生態系へ配慮した開発・発展のあり方ではない。
それは、エコロジカルな「環境的持続可能性」から拡張して、「経済的持続可能性」や「社会的持続可能性」をもあわせて総合的に実現できる発展のあり方のことである。
本書は、「持続可能な発展」のこの3要素を複合的に用いて、多様な文脈(国・地域)における「持続可能な社会」、すなわち「共生社会」に向けた実践を分野横断的に生き生きと描きだす。
<b>序 章 持続可能な発展の諸説とアジアでの展開 厳 網林</b>
?T 持続可能な発展の定義
?U SDへの接近
?V 理想と現実のギャップ
?W 新しい発展パターンの探索
?X SDモデル
?Y 本書の構成
<b>第?T部 持続可能性の概念をめぐる議論</b>
<b>第1章 アジア諸国における環境問題の様相 厳 網林</b>
はじめに
?T 行き詰まる持続可能な発展
?U アジアにおける持続可能な発展の様相
?V アジアにおける持続不可能性と複雑性
?W グリーン経済へのパラダイムシフト
おわりに
<b>第2章 持続可能な発展――インドからの視点 クリシナ・ガウダ</b>
はじめに
?T インドにおけるSDの背景
?U インドにおけるSDの諸側面
?V 環境プレッシャー
?W 持続可能な発展に向けて
?X SD推進における民間セクターの役割
結 論
<b>第3章 社会の持続的発展と日本の政策言説</b>
<b>――食料・農業・農村分野を例として 北野 収</b>
はじめに――「持続可能性」に対する疑問
?T 「持続可能性」にみるアンビバレンス
?U 農業政策の文脈における「持続可能性」概念および語法の変遷
?V 農政における「持続可能性」概念の展開とその限界
おわりに――政策言説空間と「現場」の媒介者の役割
<b>第4章 持続的発展における「持続性」と「発展性」の矛盾を解く</b>
<b>――イスラームにおける時間の観念を手掛かりに 奥田 敦</b>
はじめに
?T 直線的時間観と円環的時間観
?U イスラームにおける時間観
?V スィラート・ムスタクィームの時間観
?W 日本人の時間観・来世観
結びにかえて
<b>第?U部 アジア社会における持続可能な発展の諸相</b>
<b>第5章 組織の存続とコミュニティの持続可能性 笠井賢紀</b>
はじめに――コミュニティと組織の定義
?T コミュニティに根差した組織とは
?U コミュニティに組織が果たす役割
おわりに――コミュニティ・マネジメントのあり方
<b>第6章 メキシコ南部農村社会の持続可能な発展としてのフェアトレード</b>
<b>――社会的企業バツィルマヤ・グループのバリューチェーン構</b>
<b>築戦略を事例として 山本純一</b>
はじめに
?T チアパスとコーヒーと先住民
?U バツィルマヤ・グループと先住民共同体
?V バツィルマヤ・グループのバリューチェーン構築戦略とその課題
おわりに
<b>第7章 カンボジア地域社会の持続可能な発展と仏教寺院ネットワーク</b>
<b>――社会関係資本、住民組織と基礎教育 野田真理</b>
はじめに
?T カンボジア地域社会に内在する持続可能な発展のメカニズム
?U 地域社会内の仏教寺院と小学校のつながり
――内部結束型社会関係資本
?V 地域社会間の仏教寺院と小学校のつながり
――橋渡し型社会関係資本
?W 地域社会の担い手育成における課題と寺院コミュニティの取り組み
おわりに
<b>第8章 民主化移行期社会の持続的発展に対するイスラームの役割</b>
<b>――インドネシアにおける大学ダアワ運動を事例として</b>
<b>野中 葉</b>
はじめに
?T 政変時の大学ダアワ運動
?U 政治的イスラームの試みと限界
?V 大学ダアワ運動の拡大と継続
おわりに
<b>第9章 中国「家庭教会」の登記問題と自律的社会の復興 田島英一</b>
はじめに
?T 「新中国」という文脈と宗教
?U 建国後の宗教政策と中国プロテスタント教会
?V 「地上」と「地下」のねじれ現象
?W 「都市改革派」の登記行動
おわりに
<b>第10章 台湾社会の持続的発展における民間信仰の意義</b>
<b>――媽祖信徒組織を例として 山下一夫</b>
はじめに
?T 媽祖信仰とは
?U 新港奉天宮の成功
?V 「失敗」した北港
おわりに
<b>第11章 農林業政策からみた中国社会の持続可能性 松永光平</b>
はじめに
?T 退耕還林政策を事例とした中国社会の持続可能性評価
?U 人口・経済・環境のバランスをどうとるか?
?V 退耕還林政策開始後の食糧生産
おわりに
<b>第12章 エスニック・マイノリティにとっての持続可能性とは何か</b>
<b>――中国新疆ウイグル自治区の辺境貿易を事例に</b>
<b>小嶋祐輔</b>
はじめに
?T 開発と少数民族の周縁化
?U 周縁化に抗するための実践――辺境貿易の場から
おわりに
<b>第13章 韓国社会の持続的発展と財閥問題</b>
<b>――克服課題としての反企業情緒 柳町 功</b>
はじめに
?T 反企業情緒の実態
?U 反企業情緒の背景と原因
むすび――反企業情緒克服の道
<b>第?V部 現場からの報告</b>
<b>第14章 環境政策から見た中国の持続可能な発展と日本の環境ビジネス</b>
<b>青山 周</b>
はじめに
?T 権利意識の高まりと広がる政策空間
?U 初期段階にある環境政策
?V 制度上の特徴と課題
?W 環境をキーワードとしたビジネスの方向性
まとめ
<b>第15章 社会サービスの展開を通した都市セーフティ・ネットの構築</b>
<b>――上海キリスト教青年会の対出稼ぎ農民サービスを事例に</b>
<b>呉 建栄</b>
はじめに――出稼ぎ農民集団の現状
上海キリスト教青年会による都市の安全構築の実践
おわりに――結論と討論
<b>第16章 改革開放後の中国慈善事業の発展 劉 培峰</b>
はじめに
?T 現代中国の慈善事業の発展
?U 慈善事業発展の諸特性
?V いまだ発展が主要課題
おわりに――思考と討論
<b>第17章 日本の対中環境援助の研究 宮 笠俐</b>
はじめに――環境援助理論と研究の現状
日本の対中環境援助の背景と内容
おわりに――日本の対中環境援助の分析と評価
むすびにかえて(田島英一)
索 引
執筆者紹介
【著者紹介】
厳 網林
慶應義塾大学環境情報学部教授。専門分野:地理情報科学,持続可能な発展。
主要業績:『国際環境協力の新しいパラダイム』(編著,慶應義塾大学出版会,2008年),『日中環境政策協調の実践』(共編著,慶應義塾大学出版会,2008年),『社会イノベータへの招待――「変化をつくる人になる」』(共編著,慶應義塾大学出版会,2010年),ほか。
内容説明
「持続可能な社会」実現に向けた理論の再検討とアジアの実践。急速な経済成長の一方にある、環境問題の深刻化や格差の拡大。これらの歪みを是正し、より豊かな共生社会を築くために、何が求められているのか?地域特有の課題を通して、複合的視座から考える。
目次
持続可能な発展の諸説とアジアでの展開
第1部 持続可能性の概念をめぐる議論(アジア諸国における環境問題の様相;持続可能な発展―インドからの視点;社会の持続的発展と日本の政策言説―食料・農業・農村分野を例として ほか)
第2部 アジア社会における持続可能な発展の諸相(組織の存続とコミュニティの持続可能性;メキシコ南部農村社会の持続可能な発展としてのフェアトレード―社会的企業バツィルマヤ・グループのバリューチェーン構築戦略を事例として;カンボジア地域社会の持続可能な発展と仏教寺院ネットワーク―社会関係資本、住民組織と基礎教育 ほか)
第3部 現場からの報告(環境政策から見た中国の持続可能な発展と日本の環境ビジネス;社会サービスの展開を通した都市セーフティ・ネットの構築―上海キリスト教青年会の対出稼ぎ農民サービスを事例に;改革開放後の中国慈善事業の発展 ほか)
著者等紹介
厳網林[ゲンモウリン]
慶應義塾大学環境情報学部教授。専門分野は地理情報科学、持続可能な発展
田島英一[タジマエイイチ]
慶應義塾大学総合政策学部教授。専門分野:中国地域研究、中国市民社会論、公共宗教論、中国キリスト教系団体研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- マスティマ・ガール・コンプレックス【単…