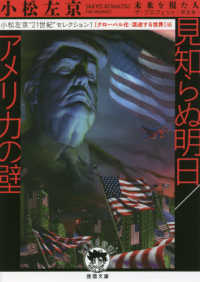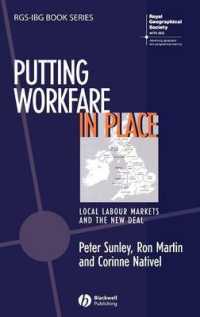内容説明
20世紀最大といわれるユダヤ系詩人パウル・ツェラン。驚くほど豊穣で繊細な詩の世界を形づくっているのは、カフカ、フロイト、ベンヤミン、アドルノ、ブーバー、ショーレムといった数々のユダヤ人たちのテクストなのである。詩人の言葉に織り込まれた膨大な引用を丁寧に読み解いていくことで、「ユダヤ精神」なるものを明らかにする。
目次
第1章 薔薇―パウル・ツェランという傷
第2章 アーモンド―ツェランとマンデリシュタームの対話
第3章 アウシュヴィッツ―ベンヤミン、アドルノと対峙するツェラン
第4章 シェヒナー、あるいはユダヤの母なる存在
第5章 モーセ、あるいはユダヤの父なる存在―フロイトとカフカを読むツェラン
第6章 カバラ―ツェランとゲルショム・ショーレム
第7章 エルサレム―「エルサレム詩篇」を読む
結語 子午線―円環を描く言葉の道筋
補遺 その他のユダヤ人たち
著者等紹介
関口裕昭[セキグチヒロアキ]
1964年大阪府生まれ。慶應義塾大学文学部卒。同大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。京都大学博士(文学)。愛知県立芸術大学准教授を経て、明治大学准教授。専門は近現代ドイツ抒情詩、ドイツ・ユダヤ文学。主著に、『パウル・ツェランへの旅』(郁文堂、2006年、オーストリア文学会賞)、『評伝パウル・ツェラン』(慶應義塾大学出版会、2007年、小野十三郎賞記念特別賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
む け
2
パウルツェランの詩は非常に難解である。地質学やカバラ、心理学や文化人類学、それに個人的に見た情景や心象風景をそのままダイレクトにぶち込んだり、変形させつつとりいれたりしているからだろうか。それでも詩自体から伝わる緊張感、気負いは相当なものだと思う。パウルツェランにとって、詩はだれかに漂いたどり着くことを意識されて書かれたものであり、間テクスト空間を開くものである。詩は理解されることを望んでおり、またユダヤ人が味わい続けてきた苦悩を理解するための努力が読み手に賭けられているのだ。ここから詩集をどう読むかが課2013/02/16