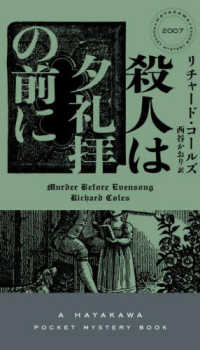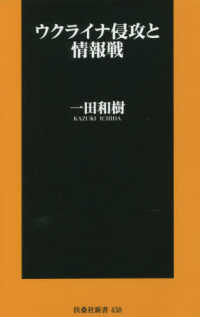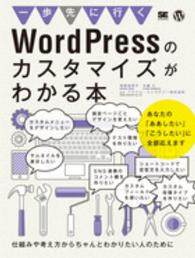出版社内容情報
大日本帝国の統治下にあった台湾・南方における、クレオール文学論。清朝、日本、国民党と統治者が入れ替わった植民地・台湾を主な舞台にした多種多様な〈日本語〉テクストの精読から、言語・文化の異種混迷性(クレオール)の中に立ち現われる〈他者〉の他者性を描ききる意欲作。
内容説明
大日本帝国の統治下にあった台湾・南方における、クレオール文学論。「内地」の作家、台湾育ちの「外地」の作家、日本語で教育された台湾人作家。この3つの視点を併せることで、清朝、日本、国民党と統治者が入れ替わった台湾を主な舞台にした多種多様な「日本語」テクストの精読から、間文化の複合、言語接触(クレオール化)の中、「ハイパーコロニアル」というべき空間となった植民地体験の実相を浮上させる渾身の力作。
目次
第1部 日本人が描いた“帝国”(「南方」の系譜;「土人」の懐柔;南方の作家たち)
第2部 在留日本人のアンビヴァレンス―西川満(西川満と『文芸台湾』;ジェンダー、修史、ロマンティシズムへの関心)
第3部 台湾人が描いた“帝国”(言語政策と文化的アイデンティティ;郷土文学派―楊逵と呂赫若;皇民文学派―周金波と陳火泉)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
2
ふむ2022/08/30
kenken
2
第1部は広く「南方」と日本人作家の出会いを描いたもので、東南アジアとの関係を考えるうえでも極めて重要。第2・3部は日本人、台湾人による日本語文学。植民地支配とそれへの抵抗という二分法で語られがちな作品群をジェンダー、階級、近代化、それに言語(日本語で書く以外に手段がないが日本人にはなれない)から見事に切り分けている。作品の選び方が秀逸で、とくに反植民地的要素が少なくあるいは積極的に皇民化を受け入れる姿勢を示した作品を、社会的背景を踏まえ再評価している。台湾=親日なんて単純な見方は恥ずかしいと思うべき。2012/05/13
yagian
1
もし、大学の文学部に入りなおすことができたら、多言語環境での文学(特に、植民地文学)で卒論を書きたいな。2011/09/22
-

- 洋書
- ALOISE