出版社内容情報
「認知症は絶対になりたくない病気」というネガティブな気持ちを高齢者がもつだけでなく,認知症になった本人やその介護家族をはじめ,ケアスタッフや介護・看護などの医療職も,認知症に対してネガティブなイメージを抱いてしまっています.
本書は,認知症の理解やケアにポジティブ心理学の考え方を取り入れることで,そうした認知症に対するイメージをポジティブなものに変えていくこと,認知症に対する見方を180°変えていくこと(「認知症になれるまで長生きできてよかった」)を目指すものです.
認知症という病気だけに目を向けるのではなく,認知症の人を支える側が認知症の人の気持ちを正しく理解してポジティブに接し,大変な中にも小さな幸せを見つけることで,認知症があっても役割や生きがいをもち,本人が住み慣れた地域で明るく穏やかに暮らし続けることにつながり,本人を支える家族や介護スタッフの負担の軽減にもつながることを紹介します.
介護が「認知症の人に〇〇してあげる」から,「認知症の人と〇〇する」になり,さらに「認知症の人が〇〇する」という本人主体のものへと進化している中,豊かな老後の暮らしを自ら考え,社会に貢献しながら生きがいを感じつつ,笑顔で生ききることを願う方々や,認知症の人を支える介護家族,そして,彼らをサポートするすべての医療・ケアスタッフ必読の書となっています.
-

- 電子書籍
- 工芸職人《クラフトマン》はセカンドライ…
-
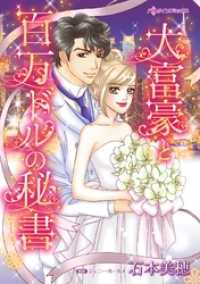
- 電子書籍
- 大富豪と百万ドルの秘書【分冊】 8巻 …
-
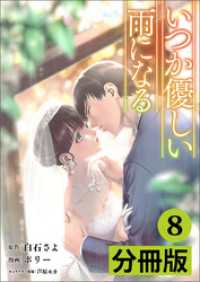
- 電子書籍
- いつか優しい雨になる【分冊版】(ラワー…
-

- 電子書籍
- 月刊正論2020年12月号 月刊正論




