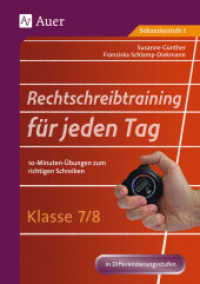- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学外科系
- > 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
出版社内容情報
《内容》 本書は「臨床家による臨床家のためのシリーズ(For clinicians by clinicians series)」の第2巻である.臨床家にスピーチと言語の障害に対する自分の治療方法について語る場を提供しているこのシリーズにおいて,今回の主題は構音障害(articulation disorders)である.序文によれば,構音障害という用語は,半世紀以前にdyslaliaという臨床用語にとって代わったものであり,近年,Shiribergらが,さらにこの構音障害を音韻障害(phonological disorder)という用語に変えることを提案している.また,構音障害という用語はその使用のされ方によって少なくとも4つの意味を持ち,第1には,誤ったあるいは標準的ではない構音のパターンに関する言語障害,第2に異なったさまざまな社会的・器質的原因により生じる障害,第3に治療上の問題領域を区別して使うもの,第4にスピーチ産生過程のどの点で問題が生じているかによって区別して用いるもの,としている. 本書において,それぞれの章を担当執筆した専門家は,その領域に関して理論的な背景を持ち,主要な治療法を実際に臨床の場面で行っている言語治療の臨床家達である.本書は,これら臨床に即して書かれた内容を,各章ごとにわかりやすく解説をつけ,編集されたものである.子どもや成人にみられる広範囲にわたる構音障害や音韻障害を取り上げており,構音と音韻障害についてさらに進んだ勉強をする臨床家には必携の書であるといえよう. 翻訳者らは日常の言語臨床の場で構音障害の問題に取り組む機会の多い臨床家達で,勉強会で本書をテキストとしたのをきっかけに,日本の多くの臨床家に読まれることを願い日本語版の出版となった.ひとつひとつの単語,文,段落を注意深く吟味し,英語版の内容や意味をより忠実に,そして正確に再現した妥協を許さない仕事は,原著編者も賞賛するところである(『言語聴覚療法』第10巻第2号 四十住 緑著「書評」より抜粋). 合計20章から成る本書の執筆者は総数23名にのぼり,そのいずれもが長年の臨床経験のふるいにかけられた理論・仮説に拠って立つ独自の治療法を実践しているベテランの臨床家である.前半の13章は広い意味での機能性構音障害と呼ばれてきた問題に関わるものであり,次のようなテーマが含まれている.構音治療における聴覚弁別の役割(1章,2章),フィードバック過程と治療手順(3章),多数の音に構音障害があるため発話明瞭度の極端に低い子どもに対する治療手順,および、発達音韻論の枠組みの中での評価・訓練法(4章~6章),調音結合の理論に基づく構音訓練(7章),構音獲得と般化の原理(8章,9章),キャリオーバの理論と訓練手順(10章~12章),個別プログラムを書くためのコンピュータ技術の利用(13章)などである.後半の各章では,いわゆる器質性構音障害の問題が取り上げられており,口蓋裂児・者にみられる構音障害の評価・訓練指針(14章,15章),成人の後天性構音障害(進行性または非進行性)に対する治療的働きかけの目標設定,ならびに代替手段を含めた複数の治療選択肢(16章),運動障害性(麻痺性)構音障害の訓練手順(17章,18章),発語失行症の評価と訓練法(19章),そして早口症の問題(20章)が,それぞれ論じられている. こうした構成から明らかのように,本書の持つもう一つの特徴は,編著者であるWinitz博士自身の構音障害に対する考え方とその基盤をなす理論的背景が各章の配置・構成に如実に反映されていることである.構音障害の臨床に関わる多様な問題を取り上げ,そのおのおのについての理論・仮説の説明を中心とする章,長年の臨床活動を通じて選び抜かれた効果的な手順の紹介に焦点を絞った章,などの巧みな組み合わせにより,全体として、臨床の現場で遭遇する構音障害の問題の間口の広さと奥行きの深さを読者の前に提示してみせる.言語病理学の牽引役をもって任ずるアメリカにおける臨床家の層の厚みを実感させる好著といえよう(「音声言語医学」35:220-220、1994 笹沼澄子著 「図書紹介」より抜粋). 《目次》 第1章 語音弁別の検査と訓練:その必要性 Lorraine M.Monnin 著 第2章 構音訓練における聴覚に関する検討 Harris Winitz 著 第3章 運動・感覚の目標と知覚の問題について Gloria Borden 著 第4章 発話明瞭度と多数音構音障害の子ども Marilynn Schmidt 著 第5章 重度構音障害児における音韻発達の促進 Barbara Williams Hodson 著 第6章 多数音構音障害の訓練 Donald Mowrer 著 第7章 調音結合に基づく構音訓練 E.Prather and P.Whaley 著 第8章 構音障害児の治療における個人の多様性について J.E.Bernthal and N.W.Bankson 著 第9章 構音訓練における般化 B.K.Rockman and M.Elbert 著 第10章 意味的対比法による構音治療 Edwin A.Leach 著 第11章 メディアの使用による訓練室の拡大 Susan J.Shanks 著 第12章 構音訓練における親や関連スタッフの効果的な活用 Babara Hartmann 著 第13章 一般法94-142:コンピュータ化された教育プログラム James M.Caccamo 著 第14章 鼻咽腔閉鎖不全のタイプ Hughlett L.Morris 著 第15章 機能性鼻咽腔閉鎖不全:診断と治療 John E.Riski 著 第16章 成人おける後天性構音障害の治療 Jeri A.Logemann 著 第17章 成人の運動障害性構音障害患者に対する構音訓練の選択 John C.Rosenbek 著 第18章 運動障害性構音障害の特徴と治療 James Paul Dworkin 著 第19章 発語失行症:神経(原)性の構音障害 Frederic L.Darley 著 第20章 早口症:その診断 William M.Diedrich 著
-

- 電子書籍
- 神ぷろ。 (3) MFコミックス アラ…