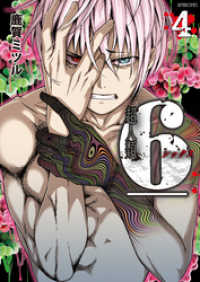- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学外科系
- > リハビリテーション医学
出版社内容情報
《内容》 次世代リハビリテーションは脳科学の進歩に連動し,その理論と技術が激しく変化していく.本書は膨大な基礎理論の中から特に神経生理学的知見を厳選してレビュー.
《目次》
第1部………………
序 章 本書のパースペクティブ
第1章 身体は脳の中で多重に,かつ可塑的に,そして生物学的な変化として再現されている
1.1 脳の中の身体の発見
1.2 身体は多重に再現されている
1.3 感覚野では身体両側からの情報が統合される
1.4 運動野にも両側性のニューロンが存在する
1.5 身体地図は再配置される
1.6 知覚は感覚の集合体ではない
1.7 経験が脳を改変させる
1.8 訓練によって身体地図は書き換えられる
1.9 脳の可塑的変化のメカニズム
1.10 脳イメージング研究における脳損傷後の機能回復過程
第2章 運動学習は脳の複雑なシステムによって実現されている
2.1 運動学習は効果器で起こるのではなく脳のシステムによって生まれる
2.2 運動学習の鍵は同側の皮質が握っている
2.3 運動学習中の脳活動の時系列性
2.4 運動学習には運動表象と運動結果の照合が必要である
2.5 運動学習のために小脳は教師役となる
2.6 小脳における内部モデル理論とはなにか
2.7 運動学習のためには離散運動が重要となる
第3章 古い小脳の知見から新しい小脳の知見へ
3.1 古典的な小脳症候学
3.2 認知的な運動制御に小脳は敏感に作動する
3.3 小脳は感覚/知覚の弁別時に作動する
3.4 心的回転と小脳活動
3.5 小脳は純粋な認知機能においても活動する
第4章 身体図式は空間認知によって生成される
4.1 形態と空間の認知システム
4.2 空間における手の運動制御
4.3 Preshapingに反応するニューロン
4.4 空間における自己参照枠
4.5 身体図式の生成
4.6 身体図式と身体イメージ
4.7 身体像のリアリズム
第5章 運動イメージは身体図式に基づいて生成される
5.1 接触せずとも物体の重量を予測することができる
5.2 接触作業が加わることで視覚による直接知覚は必要ない
5.3 物体の認知によって運動イメージが湧きあがる
5.4 物体操作の運動イメージは自らの身体図式を基にしている
5.5 経験によって身体図式は更新される
第6章 運動イメージによって脳は活性化される
6.1 運動イメージとはなにか
6.2 脳イメージング研究によって運動イメージは解明された
6.3 運動イメージの想起によりパフォーマンスは向上する
6.4 運動イメージ生成のためのいくつかの戦略
第2部………………
第7章 第2部にあたって;〈いかに知るか〉というプロセスが脳の生物学的変化の決定権を握っている
第8章 行為を生みだすための心的シミュレーション
8.1 心的シミュレーションとミラーニューロン
8.2 自分の意図の認識とはなんであろうか
8.3 一人称的運動イメージとはなにか
8.4 運動の観察と模倣は言語発達の萌芽である
第9章 言語記述は脳のシステムを監視/制御できる戦略である
9.1 脳のシステムによって行為は創発される
9.2 学習を援助するための記述科学
9.3 リハビリテーション専門家は教師でなければならない
終 章 科学的知見の解釈によってリハビリテーション・パラダイムは変わるべきである