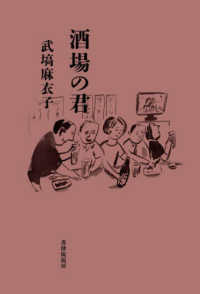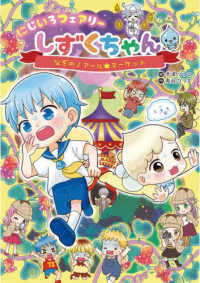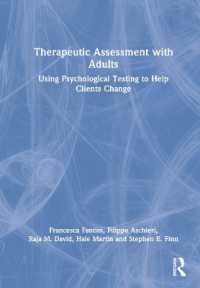- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
内容説明
ツーちゃんの成長をたどって交わされた母親と心理臨床家の10余年に及ぶ対話の時系列。
目次
1 わが子は発達障害かもしれない
2 療育を始めましょう
3 普通学級に入れたい
4 小学校で生活するということ
5 思春期をむかえて
6 中学への扉
7 中学校、不登校
8 なぜ勉強をするのか
著者等紹介
五十嵐一枝[イガラシカズエ]
白百合女子大学文学部教授。白百合女子大学発達臨床センター長。金沢大学教育学部卒。日本女子大学大学院修士課程(児童学専攻)修了後、東京女子医科大学に小児科児童心理相談員として2001年まで勤務。大学附属病院における心理臨床とてんかん児の認知発達障害の研究を行なった。2001年4月より現在まで、白百合女子大学文学部(発達心理学専攻)教授、2002年4月より2006年3月までおよび2010年4月より現在まで同大学発達臨床センター長を兼務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鳩羽
4
知的な遅れのない発達障害を、当時は軽度発達障害と呼んでいたようで、後に自閉症、アスペルガーという表現も出てくるが、幼児期はどちらかというとADHDらしさが強く出ていたツーちゃんの臨床記録。臨床心理士とママの電話やFAXでのやりとりは切実。幼児期、小学校、中学校とそれぞれの問題が出てきて、情緒級で不登校だったのを通常級に戻ったりなど、ツーちゃんの発達の状況に合わせて対応できたのが良かったのだなと思わされる。伸びる時期に、治療と教育でちゃんとフォローできるかどうか。2023/02/26
カイザー
1
タイトルの通りです。発達障害の重さに関わらず、早期の介入は、ご本人のためにも、周囲のためにも重要だと実感させられる本でした。臨床心理士さんの見立てや方針も素晴らしかったですが、母子のクライアントさんらの元々持っている健気で前向きな力があってこその経過でもあったかと思います。私用の連絡先を使ってのやり取りが多く、治療関係の枠が曖昧に感じられる部分もありました。その点に関しては、著者の力量で枠を内包してやっていた印象も受けますが、それができない臨床心理士が模倣したらえらい事になりそうだと思いました。2019/02/17
黒蜜
1
発達障害の女の子とその母親のカウンセリング担当者による女の子の育ちを追った内容。 母親が隠し事無く筆者に悩みをぶつけていますが、カウンセラーらしく客観的で冷静に見ています。2012/08/13