- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
内容説明
特別支援学校の実践を参考にしながらも、小学校、中学校にある「特別支援学級」ならではの発想で展開している実践を紹介。
目次
1章 特別支援学級の現実(激増する特別支援学級;特別支援学級での暮らし)
2章 特別支援学級における異学年・小集団指導のシステムづくり(時間の構造化;場の構造化;「交流及び共同学習」で・学校内全体で;システムの考え方・つくり方)
3章 異学年・小集団指導のポイント(学級開き;朝の会・帰りの会活動;休み時間;給食;参観日;行事;教科指導;自立活動)
著者等紹介
青山新吾[アオヤマシンゴ]
岡山県内公立小学校教諭、岡山県教育庁指導課、特別支援教育課指導主事を歴任後ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科勤務、同児童臨床研究所兼務。臨床発達心理士、学校心理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
epitaph3
2
2015年121冊目。ほぼ異学年・小集団である特別支援学級の指導の一端がよくわかる本。タイトル通り、異学年・小集団の授業でどういう配慮や工夫ができるかが書かれている。交流学級との関係をおさえた小集団の時間の確保のこと。そして、異学年だからこそ発達レベルに応じた指導により、年下が年上に教えたりする場面があって、そのときに「できるできない」という観点のみではなく、多様な観点で子どもを認める事が必要ということを学んだ。2015/03/10
U-Tchallenge
1
特別支援学級は異学年の子どもたちが在籍していることが一般的である。それをたいていは一人の教師が指導する。だからこその難しさがあるのだろう。そこで、システムづくりをするという視点が必要になる。システムをつくり、子どもたちが学びを進めることができるようにする。指導する教師も準備がしやすくなる。そのような工夫の具体的な方策を知ることができた。異学年・小集団だからできることを大切にしたい、と思わされた。特別支援学級での指導について考えたい者にとっては読んで損なしの一冊である。2021/04/08
U-Tchallenge
0
特別支援学級は異学年で構成されていることがほとんどである。また、同学年でも同じ学習内容にはならないこともほとんどである。だからこそ、システムを作り、子どもたちが自ら学びを進めることができるように考えることが必要となる。そのシステムができてくると、子どもたちだけでなく教師も指導しやすくなるのではないだろうか。なかなか特別支援学級の具体的な指導について学ぶ機会はないので、とても参考になる一冊であった。2021/05/09
いいちゃん
0
教材を作ることの大切さを 改めて感じました。2019/03/21
-
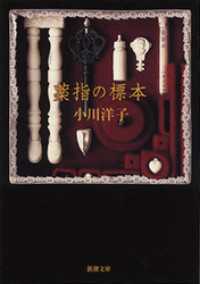
- 電子書籍
- 薬指の標本





